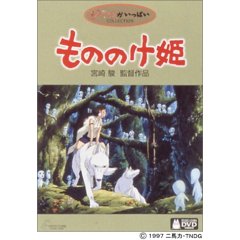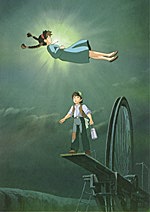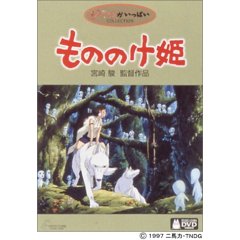

このDVDをAmazonで買う
いまさらですが。
いわずと知れた、宮崎駿の超大作。
「タタリ神」に取り憑かれたイノシシから村を守るべく戦ったアシタカは、
腕にタタリ神の呪いを受けてしまう。
呪いを解くために、村を離れ、西へ向かうアシタカ。
途中怪しい老僧に出会い、
イノシシを撃ち、タタリ神となる元を作ったエボシが束ねる村、タタラバを訪れる。
タタラバは森の木を倒し、村を守るための武器である鉄砲を作るための
鉄工場を持っていた。
森は全ての自然を司る神シシガミの住む場所であり、
人間でありながら森を守ろうとする少女サンがオオカミ親子と共に暮らしていた。
人間の暮らしを守ろうとするエボシ、
森を守ろうとするサン。
両者は相容れず、戦わなければならない運命なのか。
...この物語は人間が背負うべき「原罪」を問う物語だと僕は思う。

「がけの上のポニョ」公開に先立ち、テレビであちこち宣伝特番。
...トトロのテレビ放送もその一環なんだろうけど。
...正当なマーケティング戦略なんだろうけど。
なんかブラックなニオイがして嫌な気分になるのは大人げないのだろうか。
しかし作品そのものには罪はない。
そして今も昔も名作は名作。


このDVDをAmazonで買う
「天空の城ラピュタ」をみました。
劇場公開からもう20年も経つんですね...
何度もテレビ上映されていて、このブログでも一度記事を書いてますが。
名作は何度見てもいいもんです。
...というわけで再レビュー。

ゲド戦記を観てきました。
原作を読んですっかりファンになってしまい、
この映画の公開をずっと楽しみにしていました。
が、この映画は原作者・ル=グウィンさんをはじめかなりの
物議をかもし出しているようです。
観にいった人の感想を聞いても「よかった」「つまらなかった」など
じつにさまざま。
僕的には「面白かった」。
ただ原作を読んでいない人には確かにつまらないかも、とも思った。
アニメというジャンルから多くの子供たちが観ると思われますが、
その子供たちが果たして楽しめるか、というと疑問です。
ラピュタやナウシカのようなワクワクはない。
吾郎監督の「真面目さ」が作風に出ていると思いました。
(吾郎氏がどんな人柄なのかは知りませんが)
つまりこの映画は「生真面目すぎる」と思うのです。
生真面目すぎてツマラナイ。
でも原作に惚れ込んでいる人なら。
多かれ少なかれこの映画は観る価値があると思います。
僕はあると思った。

いまさらですが「ハウルの動く城」を観ました。
この時期になれば少しは空くかなと思ったのですが意外と混んでました。
宮崎駿おそるべし。
いい作品だと思いました。
ストーリーも。CGも。メッセージ性も。
しかし...
けちをつける気は毛頭ないのですが何かが物足りない。
優秀作品ではある。しかし感動大作ではない。
個人的にはそう思いました。
ラピュタのようなドキドキワクワクはありませんでした。
この作品はそれは意図してない、というのであればそれまでですが。
ただ、私が感じる限り昔の宮崎駿作品には
普段私たちが感じることのできないドキドキワクワクを与えてくれた。
カリオストロ然り、ラピュタ然り、ナウシカ然り、紅の豚然り。
まあ中にはトトロや魔女の宅急便、おもひでぽろぽろなどのように
ほのぼのした作品もありますがそれでもそれらの中に多少なりとも
ドキドキワクワクがあった。
それが時が経つにつれもののけ姫、千と千尋、今回のハウルと、
そのドキドキワクワクが少なくなってきてるように思えてならないのです。
宮崎作品が変わったのか、
はたまた観ている自分が変わってしまったのか...
今年の目標をもう一つ加えたいと思います。
「たくさんドキドキワクワクする」
私の「ドキドキワクワク」はどこにあるんだろう...
(2006/01/27 drecomより移動)
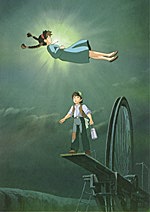
『天空の城ラピュタ』を見ました。
カリオストロ、ナウシカに次ぐ宮崎駿監督第3作目ですが
僕は宮崎作品の中でこの作品が一番好きです。
最新のCGを駆使したハウルやもののけ姫も悪くはない。
でもなにかラピュタの頃の純粋さというか、輝きというか、
そういうものにかなわない気がするのは僕だけでしょうか。
空への憧れ、人とのふれあい、わくわくするような冒険...
そして一番大切なことは僕たちは地球に住んでいるということ。
人間は地球なくして生きられないということが分かっているのに
どうしてこんなに地球を傷めつけようとするのでしょう。
最初はわくわく、見終わってテロップとともにエンディング曲が
流れる頃にはとてもしんみり。
喜怒哀楽たっぷりでそれでいて人間として大切なものはなにか、
という明確なメッセージ性も持っている。
いいものは何度見てもいい。
技術はそのすごさを伝えるためのものじゃない。
伝えたいことをより伝えやすくするためのツールなのだということを
忘れるべきではないと思います。
またラピュタのような素晴らしい名作が誕生するのを
心から願ってやみません。
(2006/01/26 drecomより移動、修正)