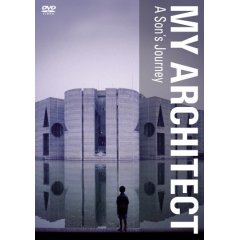この本をAmazonで買う
丸善の「建築家の講義」シリーズ。
今回はルイス・カーン。
数ある建築家の中でも、もっと詩的で哲学的な言葉を発する一人。
大好きな建築家の一人です。
本書は1968年にライス大学建築学科での講義とそれに続く質疑応答を記録したもの。
およそ40年以上もの時の流れなど、微塵も感じさせず、
今読んでもその内容は心に深く突き刺さる。
それはとりもなおさず、彼が本質を語っているから。
本当の魅力とは、本質に結びつくものでなければならない。
流行はあくまで本質へとドライブするためのトリガーであり、エネルギーである。
ルイス・カーン建築論集 (SDライブラリー)
ルイス・カーンの建築論集をやっと読み終えました。
今回はSD選書ではなく、SDライブラリー。
もっとも現在ではSD選書のほうでも同内容のものが出てるみたいですが。
SD選書の基本カラーが黒なのに対し、SDライブラリーは白です。
最初の数ページでかなりインスパイアされたのですが、
その後はライトほどまでとはいかなくともやはり難解な内容で
読むのに苦労しました。
この本は講演会でのスピーチやインタビューなどを集めた十章構成なのですが、
繰り返し繰り返し同じキーワードが登場してきます。
たぶんそうでもしなければ彼の伝えんとする本質が見えてこないからなのでしょう。
こうして読み終えたあとでもやはりその半分くらいしか彼のいわんとすることが
理解できなかった気がします。
それでもこの本から学ぶことは多かった。
人は自分自身でないものを学ぶことはできない。
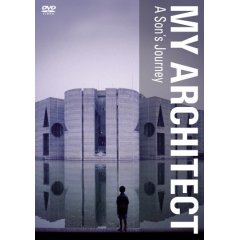

このDVDをAmazonで買う
大学の研究室にはけっこうな数の建築関係のDVDが置いてあります。
ルイス・カーンの建築論を読みはじめたこともあって、
ルイス・カーンのDVDを借りました。
このDVDはドキュメンタリー映画となっていて、
監督はルイス・カーンの息子であるナサニエル・カーン。
内容はルイス・カーンの建築を知る、というよりは
父親の建てた建築を訪れることで父親の実像を知ろう、というもの。
言うなればこの映画は息子の父親の心を知りたい、というエゴのために作られたようなもの。
しかしだからこそ、この映画は僕の心に響く。
家庭を顧みず、仕事に走った男の心中はいかようなものだったのか。
彼を取り憑かせた建築とはどんなものだったのか。

[ソーク研究所](出典:Wikipedia)
...つづいて私はこう考えました。最初の感覚は触覚であったに違いないと。おそらくそれが最初の感覚です。われわれの生殖の全感覚は触覚と関係しています。よりよく触れようと触覚が望んだとき、触覚から視覚が生まれました。見ることは、より正確に触れようとすることにほかならないのです。そしてこう考えました。われわれのなかのこのような力は美しいものであって、それは始源的で、形式のない存在から生じるにもかかわらず、なおも感覚できるものものだと。それはあなたのなかにいまもなお保持されています。(P.3)
ルイス・カーン建築論集を読みはじめました。
自分はカーンの建築をまだ知らない。
しかしほんの数ページを読んだだけで、彼の建築論を信じることができた。
建築の可能性を信じてみたいと思った。
...なぜなら最近の自分の頭の中にある、
自分がデザインしたいもの、デザインで実現したいもの、デザインで表現したいもの。
それらの中枢に「触れる」というテーマが絶えずあったから。