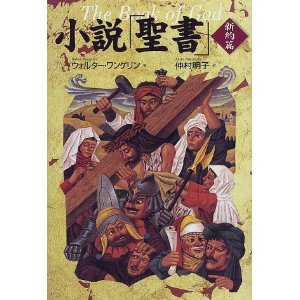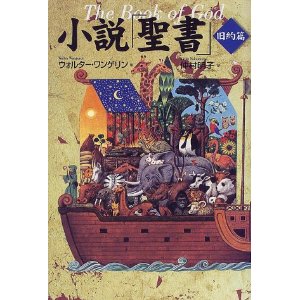徳島県鳴門市の大塚国際美術館に行ってきました。
愛媛の山奥から片道9時間(下道)かかりました。;;
この美術館は世界の名画を陶板で再現した世界初の「陶板名画美術館」だそうです。
また「行ってよかった日本の美術館&博物館」で1位に選ばれたこともあるそうです。
古代から現代までその数千点以上。
高い保存技術でその品質は二千年以上経っても色褪せないそうです。
陶板はいわば高画質プリントである。
そしてそれは、絵画がただの二次元でないことを教えてくれる。
平面のキャンパスに描かれる絵画にも「厚み」があることを教えてくれる。
絵画は「グラフィック」ではなく、「プロダクト」なのだ、と。
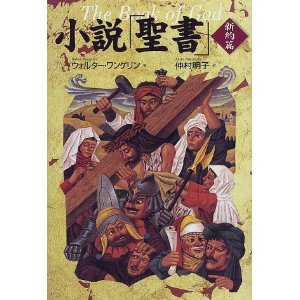
小説「聖書」新約篇。
旧約篇が主とその代々の民との長い契約の物語であるのに対し、
新約編は救世主(メシア)イエスを中心とした奇跡の物語。
正直、これまでは旧約と新約との関係がよく分からないでいた。
せいぜい旧約がキリスト誕生前、新約が誕生後、
という程度の認識しかなかった。
小説「聖書」の旧約篇、新約編を通して読むことで、
やっとその関連が分かった気がする。
それらは旧い契約、新しい契約なのだと。
旧い契約だけでは十分ではなかったから、
主は新しい契約を民と結ぶべく、神の子を地上に使わせたのだ、と。
法は守ることが第一目的ではない。
法を守ることで得られる秩序、幸福こそが第一目的である。
世は常に変化する。
だから法もそれに合わせて柔軟に変更できるものでなければならない。
しかし、本質を見失ってはならない。
愛ゆえに法がある。
法ゆえに愛があるのではない。
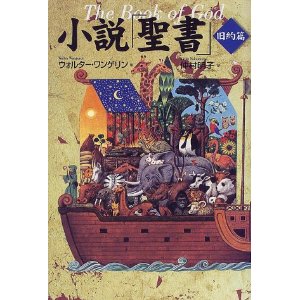
小説「聖書」旧約篇〈上〉 (徳間文庫)
小説「聖書」旧約篇〈下〉 (徳間文庫)
とくに信心深いほうではない。
むしろ、実は神については懐疑的で、
それどころか科学の発達した現代社会で、
神について考えることは、ナンセンスだとさえ思っていた。
...この歳で大学にはいるまでは。
どこにでもあるような日本の田舎町で生まれ、育った。
家の中には仏壇があり、神棚があった。
生活圏の中に当たり前のように仏教と神道が存在していた。
とくにそのことに反発することもなかったが、
積極的に受け入れることもなかった。
二十歳で上京して自由の身になってからは、
宗教とはさらに疎遠になった。
事実上無宗教といえる。
当時はそれがごく普通の、「モダン」な日本人の姿だと思っていた。
しかし、大学にはいって芸術を学ぶうちにこう思うようになった。
神を信じない人は不幸である、と。
神を信じる人は幸福である、と。

(出典:Wikipedia)
続いて好きな彫刻シリーズ第二弾。
ミケランジェロの「ピエタ」。
ミケランジェロは生涯に4つのピエタを作っているのですが、
その中でもサン・ピエトロのピエタが傑作として有名。
着衣の「ひだ」のリアルさが大理石素材と調和して
ひときわマリアの神々しさを際立たせています。
美はときに癒しをも与えてくれる。

(出典:Wikipedia)
「『おまえは鉄の武器をもってやって来た。わたしは主の御名においてやってきたのだから、おまえは主にいどむことになるのだ。今日、主はおまえをわたしの手にあたえられる。そしてわたしはおまえをたおし、イスラエルには神がおられることを地上のすべてのものが知るのだ』少年だ。ゴリアトは面食らった。唇がちぢこまった。恥をかかされた巨大な戦士の、不明瞭なうなり声がサウルにきこえた。あらたにわきあがった怒りにつき動かされて巨人は前にすすんだ。坂をかけおり、ダビデにむかっていった。若者の胸の高さに槍をかまえていた。そして右手にもった剣をふりあげた。サウルは立ちすくみ、巨人と同じように言葉も出なかった。しかしダビデは歩みの速度を変えることはなかった。投石器を頭の上でまわしはじめ、革ひもが風をきる音がした。音をたててダビデは石をはなった。石はゴリアトの頭蓋骨めざしてとんでいった」(ウォルター・ワンゲリン『小説「聖書」旧約篇』)
「好きな絵」ならぬ「好きな彫刻」シリーズ。
二次元より三次元が好きだから。
本来なら絵画より彫刻のほうが好きなはずなのですが、
好きな絵画より好きな彫刻が少ないのは、
やはり三次元での表現が難しいからだろうか。
ミケランジェロのダビデ像。
今なおその美しさは輝きを失われない。
つまりはこの頃から人間の外形は変わらず、美意識もそんなに変わってない、
ということなのでしょうか。