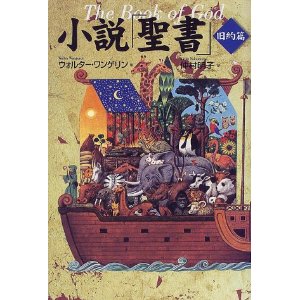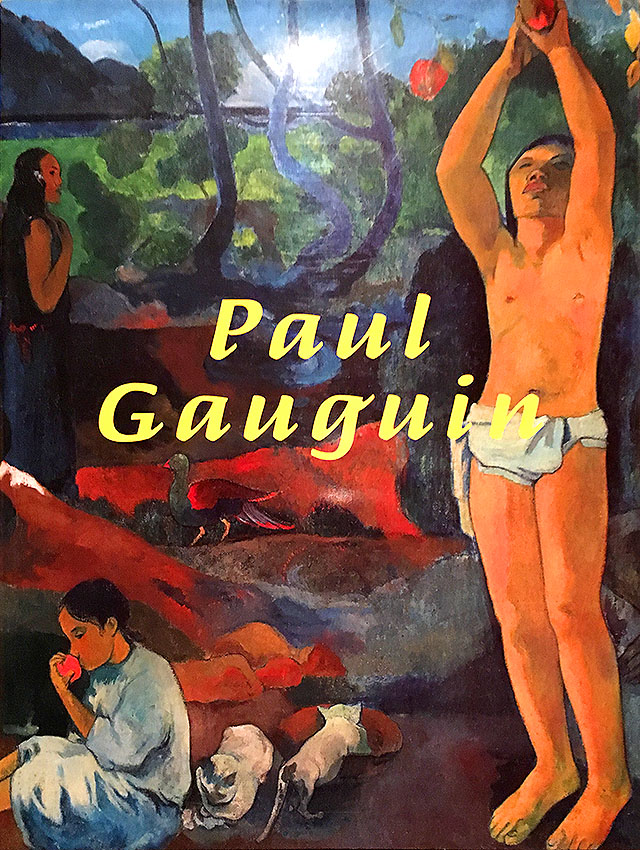この本をAmazonで買う
ウィリアム・サマーセット・モームの「月と六ペンス」。
例によって中村先生の紹介。
ゴーギャンをモデルにした小説、ということで読んでみました。
ロンドンの株式仲買人であったストリックランドは、
四十歳にしてある日突然、仕事と家族を捨ててパリに逃げた。
画家になるために。
正式な美術教育を受けたわけでもない男が、
いきなり自分の絵だけで生活していけるはずもなく、
極貧生活を余儀なくされるが、そんな苦境をものともせず、
ひたすら絵筆を動かし続ける。
何かを求め、見つけ出そうとするかのごとく。
他人からの干渉を拒み、ひたすら孤高の道を進んだ男は、
最後に行き着いたタヒチで地上の楽園を見つけ出す...
ストリックランドの人生は、
まさにゴーギャンの人生そのもののように思えるけど、
実際のゴーギャンはここまで完全無欠ではなかったように思える。
これはゴーギャンが願った理想の人生ではないだろうか。
男はなぜ平和な家庭と仕事、すべてを捨てて、貧困と孤独の道を選んだのか?
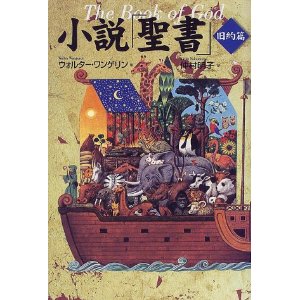
小説「聖書」旧約篇〈上〉 (徳間文庫)
小説「聖書」旧約篇〈下〉 (徳間文庫)
とくに信心深いほうではない。
むしろ、実は神については懐疑的で、
それどころか科学の発達した現代社会で、
神について考えることは、ナンセンスだとさえ思っていた。
...この歳で大学にはいるまでは。
どこにでもあるような日本の田舎町で生まれ、育った。
家の中には仏壇があり、神棚があった。
生活圏の中に当たり前のように仏教と神道が存在していた。
とくにそのことに反発することもなかったが、
積極的に受け入れることもなかった。
二十歳で上京して自由の身になってからは、
宗教とはさらに疎遠になった。
事実上無宗教といえる。
当時はそれがごく普通の、「モダン」な日本人の姿だと思っていた。
しかし、大学にはいって芸術を学ぶうちにこう思うようになった。
神を信じない人は不幸である、と。
神を信じる人は幸福である、と。

[光輪のある自画像(1889年)](画像は大塚国際美術館の陶板画)
西洋美術史Ⅱの授業も佳境。
ゴッホとくれば、当然次はゴーギャン。
精神が壊れてしまうほどの凄まじい情念で描いたゴッホが断然好きだけど、
スライドで作品を眺めていると、やっぱりゴーギャンも悪くない。
1847年6月7日パリ生まれ。
この年、二月革命が勃発、ジャーナリストだった父クロヴィスは、
革命後の弾圧を恐れて、母アリーヌの親戚を頼ってペルーへ亡命、
幼少期を南米で過ごす。
7歳の時フランスに戻り、6年間神学校で学んだ後、
17歳で船乗りになる。
23歳でベルタンの株式仲買人として働くようになり、
この頃から日曜画家として絵を描きはじめる。
25歳でメットと結婚、5人の子供に恵まれる。
26歳でピサロと出会い、印象派と出会う。
28歳にはサロンに入選。
画業に専心するために株式仲買人を辞める36歳の頃には
夫婦の間には完全な亀裂が生じており、
やがて家族とは離ればなれになる。
物質文明に嫌気がさし、
文明の及ばないブルターニュ地方の田舎町ポンタヴァンで絵を描くようになる。
しかし、小さな田舎町にも文明の波が及ぶようになると、
彼の地でも満足できなくなり、新たな楽園を求めて南国タヒチを訪れる。
2回のタヒチ滞在を経て、やがて彼の遺書と呼ばれる大作、
「我々は何処から来たのか、我々は何者か、我々は何処へ行くのか」
を描き上げる。
ゴーギャンの「狡さ」に人間らしさを感じる。
自分のエゴの追求のためには家族を捨てることすら厭わない身勝手さ。
そんな自分の身勝手さを痛いほど自覚しており、苦しむ。
そしてそんな自分の狡さを浄化するために絵を描く。
僕にはそんな風に見える。
そして、彼のそんな絵が好きだ。
親近感を感じる。
...僕の中にも「狡さ」があるから。

[ゴッホ『星降る夜』(1888年)](画像は大塚国際美術館の陶板画)
国立新美術館で開催されている、オルセー美術館展に行ってきました。
実は3年前に東京都美術館で開催されたオルセー美術館展にも行きました。
その時は美大に入る直前で、絵に関する知識も感覚も
今に比べるとまったくない状態だった。
今回はその時よりも10倍も絵画鑑賞を楽しめた気がする。
あらためて3年の月日の中で自分が学んだもの、を感じることができた。
別に絵を鑑賞するのに特別な知識なんて必要ない。
だけど、画家がどんな思いでその絵を描いたのか、
どういう時代背景でその絵を描いたのかを知れば、
よりその絵に対する思い入れが強くなる。
そして絵画で何を表現しようとしたのか、自分なりに考えることができるようになる。
感じて、考える。
「より良く」生きるために。
ただ、ボリュームとしては前回の方が大きかったかな。
けっこう混雑した中でもじっくり鑑賞したつもりだったけど、
鑑賞時間はトータルで2時間かからなかった。
いい絵はデジタルデータでもその良さが伝わるものだけど、
いい絵の本物はもっと良い。
絵は基本的に二次元の媒体だけど、
「本物の絵」は微かに三次元であり、その微かな部分に魅力が詰まっている。
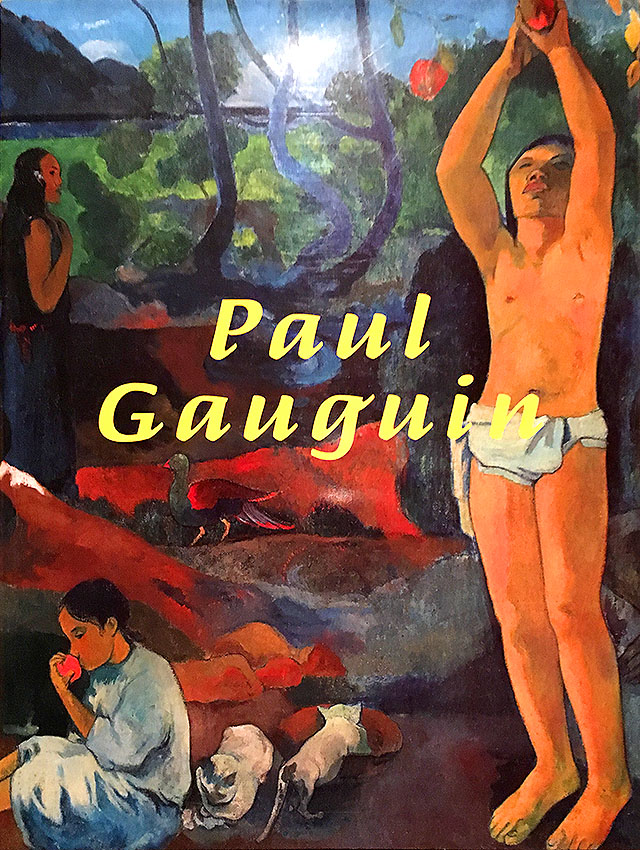
[図録 2200円]
「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか」
ゼミの展示の撤収も終わり、一段落したところで。
久々にアート系の展示を観にいきました。
久々の東京国立近代美術館。
ゴーギャン展。
正直ゴーギャンはそれほど好きではないのですが、
中村先生からタダ券をもらったので。
印象派の絵が一番好き。
エゴと客観とがほどよくバランスがとれている気がして。
印象派以前はいかに模倣するか、いかに客観的であるかに重きを置き、
印象派以後は過度にエゴが露出してゆく。
とくにゴーギャンの時代はポスト印象派(後期印象派とも呼ばれるみたいですが)と
呼ばれ、ゴッホやセザンヌらと共に印象派の持つ客観性を離れ、
より自己の内部へと向かう。
客観的すぎる絵画は退屈だし、
かといって極端なエゴは自分の好みに合えばはまるけど、
そうでなければどん引きしてしまう。
自己と他者のほどよい調和の美しさが印象派の絵にはある気がするのです。
しかし。
「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか」
この人類の永遠のテーマには誰の心にも突き刺さるはず。
もちろん自分にも突き刺さった。
いくら考えても完璧な答えなど出てこないのに。
昨日出た答えは今日にはもう違う答えになっている。
この命題はメビウスの環のごとく、永遠に続く。

東京都美術館で開催中のオルセー美術館展。
会期終了3日前にしてようやく行ってきました。
1週間前にも訪れた上野公園ですが、その時は鮮やかだった桜色も
新緑と混じりあい、すっかり色褪せていました。

1週間前は入口前まで行きながら混雑ぶりにあきらめて帰らざるを
得なかったわけですが、今回は開館後30分の9:30に行ったら
待ちなしで入れました。
それでも会場内はそれなりに人だかりができてましたが。
本展オフィシャルサイトで携帯壁紙をダウンロードして、
チケット売り場にて提示すると大人当日券で100円引きになります。
んでこれがチケット。

会場内は例によって撮影禁止、音声ガイドも500円と有料。
ホント日本って美術に対する理解が足らない...
オルセー美術館はフランスはセーヌ河をはさんでルーヴル美術館の対岸に
位置する美術館で、もともと万博のために作られたオルセー駅舎を
改装したものだそうです。
世界屈指の印象派コレクションを擁する美術館だとか。