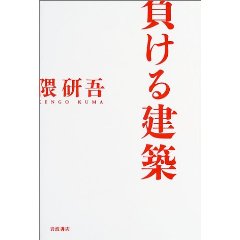隈研吾氏の「負ける建築」を"やっと"読んだ。
まだ建築に興味を持つ前の頃から、
安藤忠雄と隈研吾の名前は知っていた。
それほどこの二人の建築家の名前は社会の中でブランド化していた。
しかし今の自分は「ブランド」に対しては懐疑的。
この本の存在はけっこう前から知ってたけれど、なかなか手を出さずにいた。
「負ける建築」というネガティブなタイトルも好きになれなかった。
前回の個人美術館の課題で等々力の村井正誠紀念美術館を見学して、
隈氏の建築に触れる機会を得た。
そしてその空間の素晴らしさに魅了された。
そして現在乃木坂のギャラリー「間」で開催されている隈氏の個展。
「有機的」を意識した氏の建築にさらに惹かれていった。
氏の建築思想をもっと知りたいと思った。
タイトルからエゴ丸出しの主観的な本かな、と思ったら、
全くの逆で、主観を殺し、あくまで客観的な語り口調。
自分の建築作品についてはほとんど語られていない。
その客観性が逆に自分の言説が絶対正義だという傲慢に写らなくもない。
そして建築家特有の文章の難解さ。
東大院卒のインテリだけに知性溢れる文章なんだけど、
決して読者には優しくない。
そしてこの本はすべての建築を志す者に夢を与える本ではない。
建築の現実の厳しさを説き、それでも君は建築を志すか?と読者に問う。
まさに子供を谷底に蹴落とす獅子のようなスタンス。
この本には賛同できる点が多い反面、疑問に思う点も多々。
いずれにせよ、この本は多くのことを考えさせられる。
その意味においてこの本は間違いなく良書といえる。
建築を志す人にぜひとも読んでもらいたい。
そして読んでどう思うか。
その声を聞いてみたい。

[亀老山展望台]
本書は3章構成。
以下各章ごとに印象深かった言葉を抜粋し、
自分の思うところ、感じるところを述べていきます。
Ⅰ 切断、批評、形式
建築はその大きさゆえに、「目障りである」「物質の浪費」「取り返しがつかない」という
3つの宿命を述べることから物語ははじまる。
タイトル通りやはりネガティブな本なのか?
建築の本質は切断されるところにあるのだろうか。
まずはそこを疑うところから未来の理想的な建築は生まれる。
なぜなら、これまでの建築は自然から「切断」することで様々な弊害を生んできたから。
われわれに今、要請されているのは、オブジェクト指向と同型の思考方法、すなわち場とオブジェクトとを分割しない思考方法である。場と物の境界は曖昧であり分割不可能である。世界が複雑になるとは、そのような状態をさす。物、建築、都市はすべてほぐしがたい形で、癒着している。実際にはさらに、それらに関わる情報、欲望までもが、わかちがたく重層し、溶融し、そこに場と物という図式をあてはめること自体がすでに意味を失っている。重要なことは、そのように溶融していたとしても、世界は決して理解不能、計算不能なカオスではないということである。そのような複雑性が十分に処理可能であることを、コンピューターによってすでにわれわれは学習したのである。近代の都市計画、モダン・デザインの基本は分割原理であった。分割にかわる原理があることをすでにわれわれは予感している。予感しているだけではなく、演算もすでにはじまっている。(2 場と物)
はたして世界はそんなに複雑なのだろうか。
世界は太古より変わらず、変わったのは人間ではないのか?
ただ人間自らの社会だけが複雑になっており、
そのように複雑にしたのは世界でもなく、他の誰でもない、人間自身ではないのか?
これからの社会に「新しい原理」ははたして必要なのだろうか。
必要なものは最初から与えられている。
自らを複雑視しすぎて、自分が持っているものが見えなくなっているのではないか?
原点回帰という機能は自分を見失った人間に残された最後の本能ではないだろうか。
クリティカル(批評的)とは斜に構えて、社会から自己を防衛する姿勢の別名であった。斜に構える余裕は、社会にも建築にも、とうに失われたはずである。斜めから正対へ。徹底的にポジティブでアクチュアルに。(3 批評性とはなんだったのか)
批判は生物としての本能的な行為なのかもしれない。
しかし人間としては本質的な行為ではない。
批判は最終的な行為ではない。
だから批評家という職能は中途半端であり、いずれ消えゆく。
どんな分野でもその分野を切り開くのは、
徹底的にポジティブでアクチュアルに取り組む人たちだ。
そういう人たちは批評に満足しない。
自分も批評に満足しない人でありたい。
建築においても、すべては「負ける」レトリックで語られはじめた。思いこみのはげしいわがままな施主に負けた、奇妙な形の敷地に負けた、理不尽な建築法規に負けた、工事予算のなさに負けた。建築雑誌に並ぶテクスト、さながら負け自慢であり、泣き言のオン・パレードである。相手を説き伏せて自分の思想を実現したなどというテクストを書く人間は。変人扱いである。...(中略)...大切なことは負けのレトリックを競うことではない。建築はどんなに負けようが、それでもまだまだ強いという事実を自覚することである。資源やエネルギーを消費し、周囲の景観に影響を与え、ユーザーの行動や心理を規定し、そのような様々な形で建築は勝ってしまうのである。...(中略)...この宿命の自覚から、すべてははじまらなくてはならない。その上で、限りなく抵抗値の消滅した氷の上のような現実の上に、ゆっくりと、やわらかく、そっと、建築という危険物を着地させなければならない。(4 形式対自由という退屈)
悲劇は自己を正当化するために存在するのではない。
そして施工の悪条件が建築を弱くするわけでもない。
土を掘り返し、土に還らない人工物でエンクローズする現在の建築である限り、
建築は自然に対して常に強者であり続ける。
人が人に対して弱者であることは人間社会の中で解決できる。
しかし建築が自然に対して強者であることは、自然を意識しなければ解決できない。
強い建築が自然から切断されることで、人は自然を忘れた。
その弊害が今、現代社会で問題になっている。
Ⅱ 透明、デモクラシー、唯物論
第Ⅱ章は具体的な建築家、建築様式、建築物を挙げることで、
建築の実体を説きます。
残念ながらわれわれが生きている空間はそれほどに透明ではない。戦争に取って代わったのは平和ではなくてセキュリティー管理であった。透明性ではなくセキュリティーが空間を支配するのである。ネットによって一つにつながったかに見えるが、実際のところ世界はセキュリティー・システムによって囲われた無数のエンクロージャーに分割されている。エンクロージャーからこぼれ落ちたすきまはムーヴマンのための自由な空間どころではない。エンクロージャーのすきま、そのほころびは暴力の場でしかない。暴力をかろうじて排除した、こぢんまりとしたエンクロージャーの中でのみ、われわれはかろうじてデ・スティルのすきまとたわむれることができる。その場所とて、いつ暴力にさらされるか、誰もその安全を保障することはできない。ネット社会の平和とはこの種の平和である。ネット社会の透明とはこの種の透明である。透明はいまだ幻想の域を出ていない。(1 淋しいほどに透明な/デ・スティル)
デ・スティルとコルビュジエやミースなどのモダニズムとの比較。
勉強不足でデ・スティルの透明性はイメージできないのだけど、
造形的な洗練性にもかかわらず、
新しいテクノロジーを武器としたミースやコルビュジエにデ・スティルは敗北した。
というのはなんとなく理解できる。
ただ負けたからといって、隈氏はデ・スティルを非難しているわけではない。
那珂川町馬頭広重美術館や村井正誠記念美術館、サントリー美術館など、
氏の建築にストライプが多用しているのは、デ・スティルの透明性に
インスパイアされている部分があると感じるのは僕だけだろうか。
シンドラーは、失敗した建築家である。彼は様々に、そしてたびたび失敗した。なぜ、彼は失敗したか。それは彼がデモクラシー(民主主義)の建築家であったからである。民主主義は失敗を繰り返した。失敗を繰り返すべく、運命づけられたシステムであった。それゆえシンドラーも失敗を繰り返したのである。...(中略)...20世紀の建築とはいかなる建築であったかと問われれば、民主主義の建築であり、その失敗の実体化であったと僕は答える。(2 デモクラシーという幻想/シンドラー)
この項もルドルフ・シンドラーという建築家をよく知らないので、
イメージしにくいのだけど。
民主主義の建築をしたシンドラーと、民主主義の建築を見限ったライト。
後に世界的に名を残したライトを思えば民主主義の建築は失敗したのかな、と。
「民主主義の建築」とはなんだったのか。
たぶん「マスプロを意識した建築」ということなのだと思う。
シンドラーはPC(プレキャストコンクリート)にこだわった。
しかしあらゆるものがマスプロ化していく中で、
建築はその大きさ、強さゆえにマスプロ化には至らなかった。
その「失敗」ははたして忌むべき失敗なのだろうか。
人間を囲う建築がなにもかもを均質化するマスプロに負けて良いのだろうか。
その後のライトの功績を思えば、僕にはそうは思えない。
なぜコンクリートはかくも否定されるのか。コンクリートは構造的、施工的に優れた可塑性の高い連続体であったがゆえに、合理主義と神秘主義とを、工業と芸術とを安易に接合させたからである。そしてその接合がモダニズムを沈滞させ、モダニズムを芸術という罠にからめとり、建築の民主化を遅らせたのである。それ故に彼は否定するのである。内田はこの安易な接合を再び切りはなすことを試みた。そうすることによって日本のモダニズムを救出しようとしたのである。(3 デモクラシーの戦後/内田祥哉)
やはり内田祥哉をよく知らないので上手くイメージできず。
ただ、コンクリートへの懐疑の気持ちは分かる気がします。
コンクリートは建築界における「造形の自由」の象徴以上に、
「スピード」「効率化」の象徴であるように僕には思える。
高速化、効率化により確かに人間社会は高度成長を遂げた。
しかし同時に大切なものが切り捨てられたり、スピードの速さゆえに見えなくなったり
してはいないだろうか。
モダニズムの唱えた理念というものの正体は、結局のところ、建築は商品を超えた公的な存在だという宣言に他ならない。それに対して、建築は商品に他ならず、それを越えたメタレベルになど立ちようがないということを、村野は冷徹に認識していたのである。そして商品は命がけの跳躍を絶えず要請されている。その認識従って、彼は商品を誰よりもつややかにデザインしたし、既成のあらゆる建築的手法に対して絶えず批判的であり、彼の商品は緊張感を失うことがなかったのである。理念では商品は救えない。村野はそのことを熟知していた。その意味で彼は徹底した唯物論者であり、徹底したマルキシストであった。彼がモダニズムより長命であるといったのはその意味である。(4 制度と唯物論/村野藤吾)
「公」のチャンピオン、丹下健三。
一方モダニズムやポストモダニズムに迎合せず独自の道を歩みながらも
生きながらえた村野藤吾。
大好きな二人だけに甲乙つけがたい気持ちだけど。
中心と反中心。陰と陽。
どちらが大事かという問いはまさに愚問。
両者は互いを補いながら素晴らしいバランスを保ち、ひとつの流れを作った。
だからこの時代、素晴らしい建築が生まれた。
今、そういう良いバランスというものは存在するのだろうか。
建築の世界の内部(本体)と外部(看板)とを類別し、それを弁証法的に統合するというヴェンチューリのスタンスがすでに時代錯誤なのである。内部と外部という類別がすでに意味を持たないのである。その意味で、すべてが建築という現象の内部でもあり、外部でもある。すべてはとうの昔に許されている。その徹底的自由の中で、なにが可能か。ドリームセンターの悲しい風景を見ながらそのような自由について考えた。(5 場所、存在、表象/三愛ドリームセンター)
銀座には何度となく足は運んでいるのだけど、三愛ドリームセンターはよく知らない。
そんなに悲しくなるのだろうか。
今度ちゃんと見てみよう。
内と外という類別が意味を持たない、というのはちょっと極端な気もするけど、
言わんとする細かなニュアンスはなんとなく分かる気がする。
僕はどうも「インテリア」という分野に違和感を感じる。
建築というものを考えるとき、内と外は同時に考えるべきではないだろうか。
それが新築であろうと、内部の改修、リフォームであろうと。
内だけ、外だけ、というのはない気がする。
少女も行者も社会から距離を置く名人である。日本には、社会から距離を置き、その子細に巻き込まれぬための技術が、数多く用意されていた。少女と行者はその現代版である。個人参加の僕はただ、ひとつの、小さな木造建築の模型を展示した。本物の木で作った模型である。ガレキを並べるのでもなく、少女や行者のように、問題をすり抜ける手も使わず、具体的な解答の可能性に、今だからこそかけてみたいと思ったのである。(7 少女と行者/ヴェニス・ビエンナーレ2000)
大災害のガレキに少女の写真にヨガ行者のパフォーマンス。
これがはたして「建築展」なのだろうか。
マルチメディアの時代だと言って、安易に複数のメディアを掛け合わせる。
今の時代なんでもできなければならない、といって
従来の模型に加えてイラスト、写真、CG、映像...となんでもあり。
個人的にはこの風潮を好きになれない。
マルチにすれば表現の質が上がるとは必ずしも言えないのでは?
Ⅲ ブランド、ヴァーチャリティー、エンクロージャー
そこに満を持して登場したのが「公」のチャンピオン丹下健三であった。東京オリンピック、大阪万博などのきわめて「公」的性格の強い建築を、この「公」のチャンピオンが一手に設計した。建築を「公」から「私」へと取り戻そうとしたモダニスト民主主義的な夢は完全にかすんだ。丹下の一番弟子である磯崎新は「小住宅バンザイ」という辛辣なコラムを1958年に発表している。建築は徹底して公的な存在だというのが、磯崎の考え方である。小住宅を通じて世界を変えようという試みは、幻想であり、レベルの低い自己満足でしかないと磯崎は痛烈に批判した。技術力のある大企業の前に挫折していくモダニスト達の前で、丹下、磯崎と続く「公」的建築の担い手達は建築の王道を復活させた。一種の王政復古のごとくであった。その王政復古的閉塞のさなかに安藤が颯爽と登場したのである。彼が賢明だったのは「技術」を武器にしなかったことである。そのかわりに彼は安藤というブランドを作った。...(中略)...そうやって安藤は建築を「公」の領域から「私」の領域へと取り戻すことに成功したのである。彼が仕掛けた「公」への一撃は、大企業というもうひとつの「公」が介入したり横取りしたりする余地もないほどに見事に、ブランドにという装置によってガードされていたのである。(1 公・ブランド・私)
安藤忠雄氏の最初のスタートは確かに「私」だったかもしれない。
しかし今、安藤忠雄は「私」を代表する建築家だろうか。
今の彼は丹下健三となんら変わらない気がする。
一度ブランド化に成功してしまえば、その後の流れは必然的に「公」に向かう。
それが今の建築の流れではないだろうか。
そもそも建築界の状態として、「公」「私」のどちらかに傾かなければならないのだろうか。
どちらも建築の重要な側面であり、双方がバランスを保つべきでは?
建築家とは、そもそもはげしく挫折する運命にあるのだともいえる。なぜなら、建築設計の能力とは、一種の誇大妄想だからである。自分を創造主だと仮託するほどの誇大妄想が、建築家には必要とされた。言い換えれば、徹底して自分を「公」的存在だと思い込める能力が、建築家には必要とされた。そのような自信と構想力を持つ建築家が有能な建築家であり、建築教育とは、そのような誇大妄想を養成するための教育システムだったのである。にもかかわらず、ほとんどの建築家は、教育で身に着けたその誇大妄想を、実際の社会において実用に供することができない。ゆえに、彼らは、はげしく、ドラスティックに挫折するのである。建築家とは挫折を運命付けられた職能なのである。その挫折から彼らを救済するために、個人住宅の設計という仕事が創り出されたのだとみなすこともできる。個人住宅の設計とは、きわめて社会的意味の大きい、貴い仕事だと、彼ら挫折した建築家は考えるようになる。彼らが盛んに「住宅論」を書くのも、この理由からである。すべての「住宅論」は、住宅とは世の中の基本であり、建築の基本であり、住宅の設計とは大切な仕事だという論調で貫かれている。そう書くことによって、彼らはようやくのこと、救済されるのである。単に設計するだけでは救われず、どうしても書かねばいられないほどに、彼らの挫折の闇は深い。(2 風俗住宅)
建築家が挫折を運命付けられた職能だという指摘は納得できる。
実際建築という職業の入口に立った今の時点でも、
建築の大変さは良く耳にする。
しかし挫折感をぬぐうために住宅建築はある、というのはいかがなものか。
そういう建築家も確かにいるかもしれない。
でも住宅建築に誇りを持っている建築家だって少なくないはず。
いかにシニカルな皮肉とはいえ、こういう表現は彼らに失礼だと思う。
建築界にトップにいる人の発言だけに残念でならない。
夢を語るだけでは建築は実現しないのは分かっているけど、
建築そのものを貶めるような表現だけはしてほしくない。
20世紀社会を救済したのはプレファブ住宅と性風俗である。ともに他者を媒介せずに人々は救済される。少なくとも救済されたように人々は感じた。しかし、両者の間には根本的な差異があった。性風俗は取り返しがつき、持ち家は取り返しがつかないという差異である。ローンを背負いながら、多くの場合、少しも気に入らない家で一生過ごさなければならない。しかし、事態は少しずつ変化している。恋愛が進化をとげ、性風俗に近づきつつあるのである。恋愛はかつて、取り返しがつかないもの、すなわち不可逆的な行為であった。やり直しのきかないものであった。しかし、今、恋愛をそのようにとらえる男女はいない。しかも人々は恋愛にかつてのような形での他者とのインタラクションを少しも求めてはいない。恋愛は性風俗に急接近し、感情の密度は薄まり、軽やかなものになっている。恋愛と性風俗の境界は曖昧になり、ぼやけつつある。住宅もまた、恋愛が性風俗に漸近したように、軽やかになりつつある。かつて男女の関係が恋愛と性風俗に二分されていたように、住宅も建築家の設計する住宅とプレファブとに二分されていた。しかしそのどちらともつかぬ軽やかなものに変わりつつあるのである。ひとつの原因は施主も建築家サイドも自己というものの確固たる輪郭を失いつつあること。そのような曖昧な自己同士は軋轢の生じようがないのである。もうひとつの原因はリフォームという行為が一般化したことで、住宅もまた性風俗と同様に、取り返しがつくものへと転換していったことである。その時、「お相手」(建築家)に求められるのは、風俗嬢のごとき、つかず離れずの重くなりすぎない距離感である。これは決して批判でもなく、いやみでもない。住宅設計はリフォームへと漸近し、建築家は風俗産業へと漸近しつつある。それを受け入れることが、今日における良心的建築家の条件といってもいい。(2 風俗住宅)
これも残念に感じた部分。
確かに現代の恋愛観を的確についているとは思う。
しかし現代の恋愛観は本当にこれでいいと隈氏は本気で思っているのだろうか。
そしてそのような恋愛観と同じように建築もあるべきと本気で考えているのだろうか。
感情の密度が薄まる恋愛や建築に価値や魅力を感じるだろうか。
大衆の傾向に上手く迎合すれば成功はするのかもしれないけど、
大衆を導くことはできない。
優れたデザイナー(建築家)は、大衆を良い方向へ導く。
そしてそれこそが、建築家の良心ではないだろうか。
木造にはコンクリート打設の日のような「特別な日」というものはない。建物が完成した後ですら、建物は十分に弱く、人々は建物に手を加え続け、改修し続けた。逆に言えば、建築をつくるということ、建物が完成するということに特別の思い入れをする余地がなかったともいえる。夢を実体化し保障するような魔術的な力は、木造建築になかった。それゆえ、建築物が完成した後でも、人々はそこそこに自由であり続けることができた。「特別な日」というのは幻想にしかすぎず、時間とは永遠にだらだら続くものだというのが木造の時間の本質である。木造とは明るい諦めである。それは20世紀の「工業化」「プレファブ」の時間とも、全く異質のものである。工業化もプレファブも、その目的は、コンクリートと同様に固定であり「形」であった。すばやく「形」に到達したいという焦りが「工業化」の時間の本質であった。いかなる形にも固定化されないようなもの。中心も境界もなく、だらしなく、曖昧なもの・・・あえてそれを建築と呼ぶ必要は、もはやないだろう。形からアプローチするのではなく具体的な工法や材料からアプローチして、その「だらしない」境地に到達できないものかと、今、だらだら夢想している。(3 コンクリートの時間)
先の「風俗住宅」といい、
どうも隈氏はこれらからの建築は「曖昧さ」を受け入れるべき、と考えているのだろうか。
それがこれまでの強い建築に「負ける」ということなのだろう。
多様化すればするほど、1つの形に収めることは難しくなる、
というより1つの形に収めること自体がナンセンスなのかもしれない。
それでも僕はエッフェル塔の形を時代遅れだとは思わないし、
多くの人に受けいられる形は多様化の時代においてもあると思う。
ただ、昔よりもその形を見つけることが困難になっただけ。
困難だから諦める、ということは安易にすべきじゃないと思う。
とくに建築界のトップにいる隈さんにはして欲しくない。
グラナダのパフォーミングアーツセンターは本当に素晴らしい空間であると同時に
本当に素晴らしい造形なのだから。
しかし今や別世界であることの呈示は必要となくなりつつある。確固たる本世界がすでに喪失してしまったから、別世界の呈示もまた必要とされないのであり、別世界を呈示すること自体が無効となったのである。すべてが相対的な別世界(ヴァーチャル・ワールド)として漂っている。とすれば「別」という接頭語をつける必要もなければ、それをヴァーチャルと呼ぶ必要もないだろう。ただ無数の世界がある。なんとシンプルなのだろう。ある世界はフィクショナルなゴールと共同性で人々を誘惑し、またある世界は快感のリアリティーで人々を誘惑している。それらの「別世界」は「本世界」との距離とは関係なく、見事に自立している。...(中略)...美術館も銀行もパチンコ屋も、かくして透明の度合いを高め、本世界との接続、連続性を強調する。ガラス張りの美術館や「開かれた」銀行は、そういう隠された意図がデザインされたものである。独自のゴールを持つ自立した別世界にまきこまれる勇気もなく、かといって快感のリアリティーに身をまかすことをもいさぎよしとしない臆病で保守的な人々のためのガラスの箱。かといって本世界にかつての魅力や拘束力があるわけではない。本世界のエッジにたつこれらの透明なパラサイトの中で、臆病な彼らはわずかな興奮とつかの間の平安を獲得するのである。(4 ヴァーチャリティーとパラサイト)
隈氏の建築の透明性の意図がここにあるのだろうか。
世界は一つであると同時に、無限である。
物質世界が一つで、精神の世界が無数にある。
世界そのものはシンプルであると同時にコンプレックスでありパラドキシカルである。
確固たる本世界の存在を見出せない人に「良い建築」ができるだろうか。
すべての人間が物質世界に存在する限り、
どんなに透明なヴァーチャルワールドの存在が無数にあろうとも、
最終的なゴールは1つではないのだろうか。
そのゴールには確固たる本世界、素晴らしい本世界があると信じて
建築家は空間を創るのではないのだろうか。
要は写真の時代が終わりつつあるのではなく、美女コンテストの時代が終わりつつあり、美の時代が終わりつつあるということなのである。視覚的な美というものは、いかようにでも捏造できる。舞台に並べて、誰が誰より美しいと論じることは意味がない。大切なことは舞台からひきずりおろして実際につきあってみること。同じひとつの時間、ひとつのプロセスを共有することなのである。そういう体験の重みだけが、人間にとって意味を持つということを、他でもない、コンピュータが教えてくれたのである。(5 「美」の終焉)
僕は写真にそれほどのめり込まない。
たぶん捏造できるという安易さがあるためだろう。
確かに美を舞台に並べて論じるのは、建築に関して言えばナンセンスだ。
しかし美には捏造できないものもあると思う。
そして美とは視覚的なものだけではないと思う。
とくに優れた建築家にはそれがよく分かっているはず。
良い空間とは視覚的でなく、触覚的に知覚するのではないだろうか。
建築は切れているからこそ建築と呼ばれる。それゆえこの種の都市代用型の公共建築はしばしばエンクロージャー(囲い込まれたもの)とも呼ばれるのである。都市代用型公共建築の原理が閉鎖性にあるとするならば、この種のエンクロージャーは必然的に巨大化する宿命にあった。自らの内部に都市を構築しなければならないとしたならば、建築物はなによりまず巨大である必要があった。そして既得権の錯綜する既存の都市において巨大な敷地を確保しようとしたならば、必然的に敷地は都市の中心をはずれ、周辺部へと拡散して行かなければならなかったのである。...(中略)...ここに成立したシステムは、ひとつの悪循環とよんでよいほどに悲劇的である。都市の空間的貧困を建築で解決しようとしたときに、建築は巨大化せねばならず、安価な土地を求めて敷地は場末へ拡散せねばならない。結果としていよいよ都市は中心を喪失して拡散し、エンクロージャーの外部に取り残された都市空間はいよいよ魅力を喪失し、そしてさらなる巨大なエンクロージャーが要請されるという悪循環である。エンクロージャーは都市問題を解決するのではなく、都市問題の及ばない閉じた領域を作り、その結果としてかえて都市全体の環境は悪化の一途をたどり魅力を喪失し続けるのである。さらに絶望的なことに、巨大なエンクロージャーは建設費によって、そしてその後のオペレーションコストによって、都市財政を決定的に破綻させるのである。(6 エンクロージャー)
経済の発展とともに都市はその主体性を失っていった。
都市自身の進化への絶望から、個々の資本によるエンクロージャーが生まれた。
六本木ヒルズや、ミッドタウンもエンクロージャーなのだろうか。
それらは都市環境の魅力を喪失し続けるのだろうか。
隈氏の言わんとするところはなんとなく理解できるのだけど、
感覚的にイメージができない。
まだまだ経験不足、ということか。
すべての領域において、リスクはリスク自体を外部へと拡散させることによって回避される。いや、正確には回避されたのではなく、回避されたかに見える。その本質は、回避ではなく、拡散による遅延である。回避が遅延にすり替えられるのである。そのすり替えはネズミ講と同型である。そしてケインズ経済学こそ、そのすり替えのシステムそのものであった。ケインズ自身がそのことをよく認識していた。あなたの経済学は恐慌の短期的な処方にすぎず、長期的にはなにも問題を解決していないではないかという問いに対して、彼は長期的に見ればわれわれは皆死んでいるとシニカルに答えている。このすり替えのシステムが有効に機能するためには、社会全体の中で、このシステムの占有部分、すなわちエンクロージャーが相対的に小さくなければならない。しかし、エンクロージャーがある限界を超えて巨大化したとき、このシステムは破綻する。ネズミ講もケインズ経済学も、そこそこに成功している限りにおいて存続が可能であり、大きく成功したときには破綻するのである。今そのようにして、金融システムもエンクロージャー建築も破綻の危機にさらされている。危機の本質はそこにある。では、われわれはどのようにしたらこの危機を乗り越えることができるのか。マクロな経済学という形式自体が破綻した今、論理的に、その答えに到達するにはかなりの時間が必要であると思われる。さしあたり、われわれにできることは、エンクロージャーとは対極の建築のあり方、直感的に探ることである。都市の中に閉じた領域を作ることではなく、都市の中に小さな建築を無防備にさらし、都市に対して無惨なほどに建築を開く。閉じたエンクロージャーの中での透明性に安住しない。都市に対して開き、投げ出すことこそが透明性なのである。それでもまだ建築は大きすぎ、まだ何かを囲い込んでいるかもしれない。建築はエンクロージャーを指向する遺伝子を内蔵しているからである。いっそのこと、たった一個の石ころをこの現実の路上に置いてみること。どう置いたら、何が起こるかをじっくりながめてみること。そのような行為を建築デザインと呼びたい衝動にかられている。
ケインズはおろか経済学そのものに疎いので、
今一歩エンクロージャーの弊害がイメージできない。
「囲い込むもの」という意味において、建築はまさに「囲い込むもの」そのものではないか。
囲い込まない建築、というものがあるのだろうか。
世界的に高名な建築家と、まだドアの前に立ったばかりのアラフォーの建築家の卵。
建築家になれるかさえ、今の時点では皆目見当もつかない。
どちらの言葉が説得力があるか、なんてことはこれを書いてる本人が
一番身に染みて分かっている。
それでも考えずにはいられない。
この本は考えさせてくれる。
賛否両論あるけれど、やっぱりこの本は素晴らしい。
手元に置いておきたい一冊。
まだまだ勉強不足で分からないことだらけ。
とりあえずぐだぐだ考えていないで、
僕も石ころを路上に置いてみるべきなのだろう。