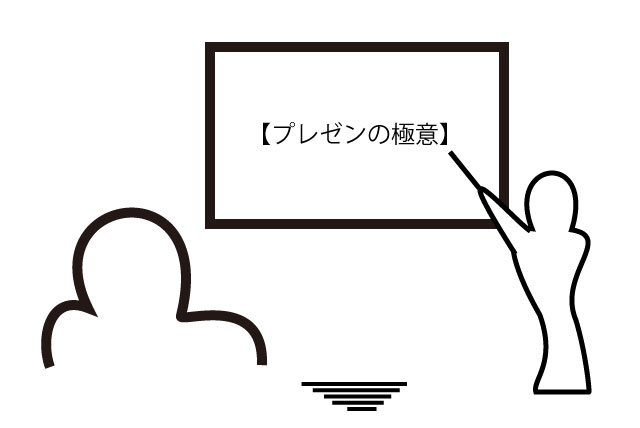
本記事は社会人学生として美大に通っている2009年に執筆したものですが、
意外とアクセスが多いので、8年経った2017年に再編集してみました。
どちらかというと、プレゼンは苦手。
人前に出ると緊張するし、
頭の中で整理しておいたことを100%伝えることは難しいし、
よしんば自分で伝えたと思ったとしても、相手に伝わっていないこともある。
デザイン学科というところはプレゼンが多い。
かつて十代で理系の高専に通っていた頃、プレゼンをした記憶はほとんどない。
プレゼンは自分をアピールする「基本的な手段」である。
※ 以前は「唯一の手段」と書いていたけど、
よく考えたら自分をアピールする手段なんていくらでもあるよね。
理系の世界が知識を積み重ねてなんぼ、というのに対し、
デザインの世界は自分をアピールしてなんぼ、という感がある。
だからデザインの世界ではプレゼンやポートフォリオが重要となる。
良い作品は作者が語らずとも自ら語るかもしれない。
しかし、そんな完璧な作品をいつも作れるとは限らない。
どんな優れたデザイナーでもそうそう作れるものではない。
だからやっぱりデザイナーにはプレゼンとポートフォリオが必須なのである。
そんなプレゼンの多い大学でありながら、
学生のプレゼンのレベルは総じて高くない気がする。
自分もそんなにプレゼンが上手いほうではないけれど。
プレゼンそのものを先生から注意されることはほとんどない。
それが年の功なのかどうかはよく分からないけれど。
若い学生達のプレゼンをそばで見ていて、
もうちょっと上手くプレゼンすれば作品の良さが伝わるのに、
...と思うことがしばしばなのでこの記事を書いてみました。
...こんな記事を書くこと自体、歳をとったということなのだろうか。
※ ここで念を押すけれど、
本記事はプレゼンが得意だからみんなにそのノウハウを教えてあげるね、という上から目線ではなく、
あくまでプレゼンが苦手な人間がプレゼンを克服するための備忘録として、
同じような思いをしている人との意識共有をしたい、という想いからのものです。
この時期に来て、先生のコメントがより辛辣になってきた気がします。
それはこれまでの大学、というぬるま湯から
社会という厳しい世界へ出ていく学生への心配であり、親心だと、
この歳で大学に通う身には、それがよく分かるのだけど、
若い学生に先生の想いは通じているだろうか。
実際自分自身、若い頃は人から説教されるのがなによりも嫌いだったしね。
「そんなこと云われなくても分かってる」
...分かっていないくせにそんな風に決め込んで自分の幅を狭めていた。
プレゼンはデザイン手法云々の話ではなく、社会人としての素養の問題である。
せっかく良い提案や作品を作っても、プレゼンをきちんとしないがゆえに、
その良さが伝わらない。
作品そのものへの評価になかなか至らないのである。
別にバリバリの営業マンや企画プレゼンターのようにやれ、というのではない。
自分だってそんな風には出来ないし、先生もそこまで難しいものを求めてなどいない。
人になにかを伝えるために必要な最低限のこと。
それは技量以前の問題である。
【プレゼンでしてはならない9箇条】
1.プレゼン開始時刻への遅刻
2.プレゼン資料の不準備、不備
3.プレゼン資料を棒読み
4.声が小さい、聞き取れない
5.だらだらと話が長い
6.プレゼン内容の欠点を話す
7.言い訳
8.プレゼン中に謝る
9.リサーチのみで自分の意見、提案がない
1.プレゼン開始時刻への遅刻

プレゼンの目的はただ「伝える」だけでなく、
相手にプレゼン内容に同意してもらい、興味を持ってもらうことにある。
それには相手に不快を与えるようなことはするべきではない。
機械を相手にプレゼンをするのではないのだから、
相手の心象を悪くすることはプレゼンの目的には不利となってしまう。
そのことを考えれば、1.がどれだけプレゼンに不利なことかは明白である。
プレゼン相手に対して失礼なばかりでなく、
事前準備が十分にできないどころか、心の準備さえもできない。
そんな状態で良いプレゼンなどできるわけがない。
2.プレゼン資料の不準備、不備

このタブーも意外と多い。
全く事前準備なしで言葉だけで説明しようとする。
それで人の心をつかむことができるのは、よっぽど場数を踏んだ人のみ。
話し言葉は思ってる以上に何かを伝えるには不十分なものである。
言葉だけのプレゼンで、高評価を得ている学生をかつて見たことがない。
言葉はメインではなく、資料を補完するサブとするくらいがちょうどよい。
話し言葉はその場限りの一時的なものだが、資料は後々残るものであり、活用できる。
資料も文字メインではなく、図や写真など直感的に分かりやすいものを多用すること。
その方が良い資料となりやすい。
また、よしんば資料を事前に用意したとしても、
データが壊れている、データが重い、表示が予想していたものと異なる...
これではせっかく用意しても、やはり相手への印象は悪くなってしまう。
あらかじめ事前確認を怠らないべきである。
3.プレゼン資料を棒読み

1.、2.をクリアしてもこのタブーを犯してはだいなしである。
どんなに良い資料でも、感情のない言葉をだらだら聞かされるのは苦痛でしかない。
どんなに論理的にテーマを突き詰めても、
最後に人の「心」を動かすのは、「心」なのだから。
アツい想いを、感情をこめて相手に訴える。
それにはプレゼン資料に長文は禁物である。
箇条書きを基本とし、口頭で簡潔に補足するくらいでちょうど良いのである。
プレゼンはパッションだ!
4.声が小さい、聞き取れない

声が小さくなってしまうのは、自信の無さからである。
どんなに良いアイデアでも、自信なさげに喋ってしまっては、やはりだいなし。
どんなに自信がなくても、それを顔に出してはならない。
それが社会人に求められる「強さ」である。
繰り返すが、プレゼンはパッションだ!
5.だらだらと話が長い

さあ、4.までクリアした。
しかし、どんなにアツく語ったとしても、
だらだらと話が長くなってしまっては、要点がぶれてしまう。
プレゼン資料同様、話す言葉も極力簡潔に、それでいて丁寧に。
プレゼンはパッションだけど、熱すぎてもオーバーヒートしてしまう。
情熱を持ちつつ、冷静さも保ちつつ。
プレゼンはバランスだ!
6.プレゼン内容の欠点を話す
7.言い訳
8.プレゼン中に謝る

プレゼンは自分の提案の「良さ」をアピールするものである。
たとえ提案に欠陥があったとしても、基本的には言わないのが鉄則である。
これは「誤魔化し」とは違う。
「完璧な提案」などないことは先方も重々承知である。
その上で、今時点でアピールできることを優先してアピールする。
それが大事なのである。
こう考えると、6.、7.、8.がいかにプレゼンに不利益か、
分かっていただけると思います。
プレゼンにおいては謙遜は美徳ではなく、積極性こそが美徳なのです。
9.リサーチのみで自分の意見、提案がない

これも意外と多い。
自分の提案がゼロから、無からはじまることなどまずない。
だから自分の提案の背景を説明することはとても重要なことである。
しかし、プレゼンの目玉はあくまで自分自身の提案である。
必要以上の背景説明は相手を退屈にさせてしまう。
背景説明、リサーチは全体の1/3程度に留めるべきである。
そして背景と自分の提案は明確に区別することである。
どこまでが背景で、どこからが自分の提案なのか。
プレゼンするアイデアの「アイデンティティ」を常に意識しよう。
これら9つのタブーを守ることは決して難しいことではないはず。
しかし意外と出来ていない学生が多い。
学校内では通用しても、社会ではこの9箇条を守らないプレゼンはまず成功しない。
繰り返しますが、これらはプレゼンの技量の問題ではなく、
プレゼンの重要性について、認識が足らないという根源的な問題だと思う。
逆に言えば、その自覚さえできれば、プレゼンの質は格段に上がるはずである。
義務感でやる限り、相手には伝わらない。
相手に同意してもらいたい、興味を持ってもらいたい、という真摯な気持ちがなければ。
もちろんその気持ちがあれば必ず伝わる、というわけでもない。
しかし、その気持ちがあってはじめて伝えようとする内容が正しく評価できる段階に至る。
成績をつけてもらうためにやるのではなく、
社会で生きていくためにやるのだ、という自覚を持つべきではないだろうか。
なにを伝えたいのかよく分からない、という学生もいるかもしれない。
そんな状態で良いプレゼンができるわけはない、と。
その気持ちは分からなくもない。
自分もそんな気分になることが今でもある。
そういう人はブログを書くことをオススメします。
こっそり隠れて書く日記ではなく、オープンなブログを。
最初は吐き出したい言葉をただ直接的に羅列するだけでいい。
もしあなたの中に何かを誰かに「伝えたい」という衝動があるならば、
そのうち誰かが読んでいるかもしれないあなたのブログを、
もっと読みやすいように、分かりやすいように工夫や整理をしたくなるはずだ。
そしてある日、誰かがあなたの伝えたいことを理解してくれたり興味を持ってくれたなら、
もっとたくさんの人に、もっと深く理解してもらいたい、と思うようになるだろう。
そうやって伝えるための整理・推敲を繰り返していくことで、
自分の伝えたいことが明確になってゆく。
デザインとは関係性を表現することだ。
自分と他者を、他者と他者を、他者と社会を結ぶ良い関係性を。
それにはまず自分の中をすっきりさせなきゃね。
そこから良い関係ははじまる。
そこから良い社会は構築されてゆく。