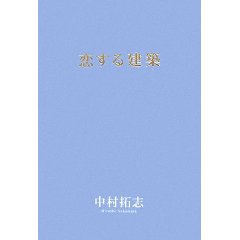コルビュジエといい、ライトといい、カーンといい、
はたまたコールハースやセシル・バルモンドといい、
どうして建築家が書く本ってあんなにわけが分からないんだろ...
と、愚痴をこぼしてたら同級生が紹介してくれた本。
中村拓志(ひろし)という新進気鋭の若手建築家が書いた本。
隈研吾事務所出身なんですね。
もちろん僕はこのときまで中村拓志氏を知りませんでした。
読んでみると確かに分かりやすい。
くぼみのある壁。
構造と意匠が一致する超薄の板材。
垂直耐力と水平耐力をそれぞれ分けたことで生まれた美しい極細の柱。
重力負荷を軽減するために天井に無数の極小穴を空けることで
生まれた美しい星空。
そのどれもがロマンチックでまさに「恋する建築」。
書いている内容も、実際に手がけた建築作品の数々も素晴らしいものばかり。
あたりまえだけど、
夢中になれるから膨大なスタディをこなすエネルギーが生まれる。
好きだからもっと知りたい、もっと良い関係を築きたいと思う。
相手との距離をどんどん近づけていくから細かいところまで見えてくる。
氏の建築の特徴がインテリアやマテリアルにあるのはそんな「恋する建築」を
目指すスタイルにあるのだなと感じました。
一方で自分は、といえば。
正直インテリアよりは外観や構造に興味がある。
恋は一過性のもの。
いつかは燃え尽きる。
そんな特性を持つ恋に建築をあてはめることに違和感を感じる。
氏はもちろんこのような恋の悪い特性ではなく、
良い特性を生かしたから成功しているのだということは分かるのだけど。
近づけば見えてくるものがある一方で、
遠ざかることで見えてくるものもある。
また、遠ざかることで見えなくなるものもあれば、
近づくことで見えなくなるものもある。
本当に大切なものは目に見えない。
近づいても見えない。
「空間」にはそんな大切なものが詰まっている。
その大切なものを感じたくて空間の周りにものを造る。
大切なものを包むその形が、大切なものの存在を伝えてくれる。
そこが建築の魅力だと思うし、その建築の支え方に興味がある。
若くして成功している氏に羨望の気持ちを持っているのも自覚してるし、
まだ学びはじめたばかりの自分の言葉より、
すでに多くの建物を建てている氏の言葉のほうが説得力がずっとあるのも
分かっている。
それでも僕は自分の本分を分かっているし、
自分がやるべきことも分かっている。
分かりにくい本を悪だと思っていた。
「建築は立派なんだけど、文章はね...」
でも分かりやすい言葉は分かってしまった時点でそこでおしまいだ。
言葉では表現できない魅力を過去の偉大な建築家たちは建築で表現してきた。
言葉にならない魅力を言葉にしようとすることは、
手がけた建築が見事であればあるほど難しい。
それでも建築の魅力を後世に残すために偉大な建築家は果敢に挑戦してきた。
これこそ真に偉大なる建築家ではないだろうか。
真に偉大なる建築家の厚意に報いるためにも、
凡人は何度でも、理解できるまで読まなきゃならないのだ。
よく分からなかった、途中で挫折した偉人たちの本を
もう一度読んでみようと思いました。