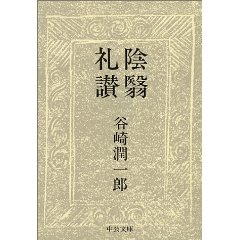大学に入ってすぐの頃、授業で紹介されたのですが、
読もう読もうと思いつつ、なかなか読まなかった本。
自由が丘のブックオフで見つけて購入し、このほどやっと読み終えました。
表題の「陰翳礼讃」ほか、
「懶惰の説」「恋愛および色情」「客嫌い」「旅のいろいろ」「厠のいろいろ」
の五編が収められた短編集。
明治以降の文明開化以後、急速に西洋文化が浸透しつつある昭和初期、
著者の主観による日本文化を西洋文化と比較しながら解説。
やはり冒頭の「陰翳礼讃」が一番秀逸かな。
...というより「陰翳礼讃」で十分、というか。
かの文豪の筆といえど、長々と読んでいたくはない文章、というか。
書いてる内容は確かに正しく説得力はあるのだけど、
聞いてる(読んでいる)方は説教されてる気になってしまう、というか。
光りそのものを賛美する文化と、光りによって生じる影を賛美する文化。
どうやら日本は本来、後者の文化らしい。
それが文明開化の波に飲まれ、西洋文化の合理主義にかぶれた。
どうやらそれが日本の悲劇らしい。


私は、京都や奈良の寺院へ行って、昔風の、うすぐらい、そうしてしかも掃除の行き届いた厠へ案内される毎に、つくづく日本建築の有難みを感じる。茶の間もいいにはいいけれども、日本の厠は実に精神が休まるように出来ている。それらは必ず母屋から離れて、青葉の匂や苔の匂のして来るような植え込みの蔭に設けてあり、廊下を伝わっていくのであるが、そのうすぐらい光線の中にうずくまって、ほんのり明るい障子の反射を受けながら瞑想に耽り、または窓外の庭のけしきを眺める気持ちは、なんとも云えない。漱石先生は毎朝便通に行かれることを一つの楽しみ数えられ、それは寧ろ生理的快感であると云われたそうだが、その快感を味わう上にも、閑寂な壁と、清楚な木目に囲まれて、目に青空や青葉の色を見ることの出来る日本の厠ほど、恰好な場所はあるまい。そうしてそれには、繰り返して云うが、或る程度の薄暗さと、徹底的に清潔であることと、蚊の呻りさえ耳につくような静かさとが、必須の条件なのである。...(中略)...まことに厠は虫の音によく、鳥の声によく、月夜にもまたふさわしく、四季おりおりの物のあわれを味わうのに最も適した場所であって、恐らく古来の俳人は此処から無数の題材を得ているであろう。されば日本の建築の中で、一番風流に出来ているのは厠であると云えなくはない。総べてのものを詩化してしまう我等の祖先は、住宅中で何処よりも不潔であるべき場所を、却って、雅致のある場所に変え、花鳥風月と結び付けて、なつかしい連想の中へ包むようにした。
こういう瞑想的空間のトイレ、今の日本では皆無だよね...
実家のぼろ家でさえ、こういう風流な厠はなく、厠は不浄の地となっていた。
それどころかバスとトイレを同じ空間に置く、という西洋の習慣を真似する始末。
トイレ空間を見直すこと。
古き良き日本を取り戻す1つのヒントなのかも知れない。

支那に「手沢」と云う言葉があり、日本に「なれ」と云う言葉があるのは、長い年月の間に、人の手が触って、一つ所をつるつる撫でているうちに、自然と脂が沁み込んで来るようになる、そのつやを云うのだろうから、云い換えれば手垢に違いない。して見れば、「風流は寒きもの」であると同時に「むさきものなり」と云う警句も成り立つ。とにかくわれわれの喜ぶ「雅致」と云うものの中には幾分の不潔、かつ非衛生的分子があることは否まれない。西洋人は根こそぎ発き立てて取り除こうとするのに反し、東洋人はそれを大切に保存して、そのまま美化する、と、まあ負け惜しみを云えば云うところだが、因果なことに、われわれは人間の垢や油煙や風雨のよごれが附いたもの、乃至はそれを想い出させるような色あいや光沢を愛し、そう云う建物や器物の中に住んでいると、奇妙に心が和やいで来、神経が安まる。
使い込むほどに味が出る。
これもかつての日本が持っていた、良い文化だった。
それがいつしか新しいものほど価値がある、といったように価値観は逆転した。
「闇」を条件に入れなければ漆器の美しさは考えられないと云っていい。今日では白漆と云うようなものも出来たけれども、昔からある漆器の肌は、黒か、茶か、赤であって、それは幾重もの「闇」が堆積した色であり、周囲を包む暗黒の中から必然的に生まれ出たもののように思える。派手な蒔絵などを施したピカピカ光るロウ塗りの手箱とか、文台とか、棚とかを見ると、いかにもケバケバしくて落ち着きがなく、俗悪にさえ思えることがあるけれども、もしそれらの器物を取り囲む空白を真っ黒な闇で塗り潰し、太陽や電燈の光線に代えるに一点の燈明か蝋燭のあかりにして見給え、忽ちそのケバケバしいものが底深く沈んで、渋い、重々しいものになるであろう。...(中略)...つまり金蒔絵は明るい所で一度にぱっとその全体を見るものではなく、暗い所でいろいろの部分がときどき少しずつ底光りするのを見るように出来ているのであって、豪華絢爛な模様の大半を闇に隠してしまっているのが、云い知れぬ余情を催すのである。そして、あのピカピカ光る肌のつやも、暗い所に置いてみると、それがともし火の穂のゆらめき映し、静かな部屋にもおりおり風のおとずれのあることを教えて、そぞろに人を瞑想に誘い込む。もしあの陰鬱な室内に漆器と云うものがなかったなら、蝋燭や燈明の醸し出す怪しい光りの夢の世界が、その灯のはためきが打っている夜の脈搏が、どんなに魅力を減殺されることであろう。まことにそれは、畳の上に幾すじもの小川が流れ、池水が湛えられている如く、一つの灯影を此処彼処に捉えて、細く、かけそく、ちらちらと伝えながら、夜そのものに蒔絵をしたような綾を織り出す。
蒔絵とか金屏風とか。
それを明るい美術館で眺めるたびに、どこが美しいのだろう?って思ってた。
本来見るべき環境で見なければ、どんな逸品もその美を失ってしまう。
私は、吸い物椀を前にして、椀が微かに耳の奥へ沁むようにジイと鳴っている、あの遠い虫の音のようなおとを聴きつつこれから食べる物の味わいに思いをひそめる時、いつも自分が三昧境に惹き入れられるを覚える。茶人が湯のたぎるおとに尾上の松風を連想しながら無我の境に入ると云うのも、恐らくは似た心持なのであろう。日本の料理は食うものでなくて見るものだと云われるが、こう云う場合、私は見るものである以上に瞑想するものであると云おう。そうしてそれは、闇にまたたく蝋燭の灯と漆の器とが合奏する無言の音楽の作用なのである。かつて漱石先生は「草枕」の中で羊羹の色を賛美しておられたことがあったが、そう云えばあの色などはやはり瞑想的ではないか。玉のように半透明に曇った肌が、奥の方まで日の光を吸い取って夢見る如きほの明るさを含んでいる感じ、あの色あいの深さ、複雑さは、西洋菓子には絶対見られない。
なにもかもクリアにしてしまう西洋の合理主義。
そのおかげで文化は誰にでも手に届く、お手軽なものになった。
でも、その代償として「想像力」を失ったのではないだろうか。
しかしそうは言っても。
西洋文明の便利さに浸り切った現代社会。
おいそれとその便利さから今更抜け出せない。
昭和初期に生きた谷崎潤一郎でさえ、すでにその便利さに浸り切っていた。
「陰翳礼讃」の最後は以下のように結ばれている。
今更何と云ったところで、既に日本が西洋文化の線に沿うて歩み出した以上、老人などは置き去りにして勇往邁進するより外に仕方がないが、でもわれわれの皮膚の色が変わらない限り、われわれにだけ課せられた損は永久に背負っていくものと覚悟しなければならぬ。尤も私がこう云うことを書いた趣意は、何等かの方面、たとえば文学藝術等にその損を補う道が残されていはしまいかと思うからである。私はわれわれが既に失いつつある陰翳の世界を、せめて文学の領域へでも呼び返してみたい。文学という殿堂の軒を深くし、壁を暗くし、見え過ぎるものを闇に押し込め、無用の室内装飾を剥ぎ取ってみたい。それも軒並みとは云わない、一件ぐらいそう云う家があってもよかろう。まあどう云う工合になるか、試しに電燈を消してみることだ。
本書が書かれた昭和初期よりもさらに格段に進化した文明の下に暮らす僕らは、
さらに強力な「便利」の鎖に縛られている。
はたして縛られたままで良いのか。
高度な文明が世界を窮屈にしているのではないだろうか。
「便利さ」が却って僕らを不自由にしてはいないだろうか。
「便利さ」が却って僕らの想像力(創造力)を狭めてはいないだろうか。
一人の文学家が記した随筆ではあるけれど、
デザインの本質が、空間(建築)の本質が、この「陰翳礼讃」には詰まっている気がする。
幸せの度合いは「光」の強さで決まるのではなく、
「陰」のつくりかたで決まるのではないだろうか。