20世紀の建築家の三大巨匠の一人、ル・コルビュジエの名著。
...しかし僕にとってはコルビュジエの文章は難解なこと、この上ない。
「モデュロール」「輝く都市」を読む限りは。
彼の描く絵と同じくらい不可解に感じます。
一方で彼のいわんとすることもなんとなく分かる気もする。
建築を考えていく上で大切なもの、必要不可欠な要素を与えてくれる気もする。
それは彼が実際に建てる建築が、
言葉以上に語りかけてくるからではないでしょうか。
「錯乱のニューヨーク」でコルビュジエが出てきて、
コルビュジエについて再考してみたいと思い、
代表作でありながら未読だった本書を読みました。
コルビュジエ、ミース、ライト。
この3人が巨匠たらんとするところは、
建築の機能を飛躍的に拡大すると同時に、
建築に偉大な哲学を取り入れたことではないでしょうか。

「開かれた手の碑」(出典:Wikipedia)
「飛行機や船が工業化により進化するように建築も進化しなければならない。」
...今の時代こんなことを言っていたら笑われるだろう。
他の分野と同じように住宅も工業化により進化した。
しかし人類は今幸せだろうか?
幸せでないなら、その理由はやはり技術力が不足しているからだろうか?
答えがノーだということに今の時代の人間たちは気づきはじめている。
技術は必要だ。
しかしそれだけでは不十分だ。
快適な空間。
利益を生み出す空間。
長年使える空間。
安全な空間...
建築の持つ「機能」を技術力はどんどん強化した。
1920年代にそれを提唱したコルビュジエの手腕はたいしたものなのかもしれない。
しかし彼の真価はそこにあるのだろうか。
「住宅は住むための機械である」
この言葉に囚われすぎてはいけない。
この言葉はある意味真実であり、ある意味では警鐘でもある。
その機能を飛躍させるために、建築は機械の力を利用した。
しかしその機能を向上させたのはなんのためだったのか?
人々が幸せになるためではなかったか?
サヴォア邸を建て、「近代住宅のための五原則」を唱え、
ユニテ・ダビタシオンのような巨大集合住宅を建て、
デカルト的摩天楼による都市計画にまで構想を広げ、
科学による建築の飛躍を目指した前半生も、
後半生では少し毛色の違うものとなっていった。
実際に実現したインドの計画都市チャンディガールには
デカルト的摩天楼はおろか高層ビルすら現れないし、
ロンシャンの礼拝堂にマスプロの象徴はなく、
逆に造形の可能性を追求した芸術的な象徴がそこにはあった。
そして妻に捧げたカップマルタンの小さな家。
コンクリとアスファルトで固められた空間は、
一見快適な空間を実現したかのように見えた。
しかしそれは違った。
進化した技術で、進化した環境で人は豊かになったはずだった。
しかし実際は心を病む人間がなんと多いことか。
人が幸せに過ごすには、ただ人だけが快適になればいいのではない。
その空間の周囲が、自然が、地球が快適でなければならない。
今はそこまで考えなければならない時代になっている。
建築により実現される空間には「愛」がなくてはならない。
そこに愛がなければ、どんなにオシャレであっても、
どんなに経済的であっても、どんなに安全であっても、
良い空間とはいえない。良い建築とはいえない。
人にとって、周囲の環境にとって機能的であると同時に、
建築は愛を伝えるシンボルであり、モニュメントでなければならない。
...チャンディガールの「開いた手」はそう語っている気がします。
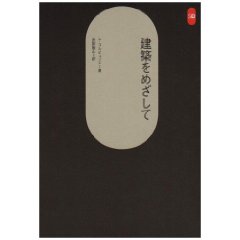
コルビジェ
リプロダクト家具コルビジェのlc2ソファを通販で買おうかな?