
TOKYO ART BEATで知って、見に行ってきました。
リサーチより手を動かしてモノを作れ、という段階なのですが、
ちょうど卒業制作で自分が創りたい、と思うものに近いイメージだったので、
どうしても見に行きたかったので。
場所は表参道の「Gallery 5610」。
spiralの真裏にこんな素敵なギャラリーがあったんですね。
spiralの正面側は良く通るのだけど、裏側は今回はじめて訪れました。
東大大学院農学生命科学研究科というなにやら小難しそうな研究所の
社会人向け木造建築コースの学生さんたちの作品展示らしい。
ギャラリーの内部に模型展示がしてあって、
外の中庭に実寸モデルの作品が3つほど展示してありました。
これこれ。
こういうことをやりたかったんだよ。

地下にも入口らしきものが...

近づいてみるとドア一面に文字が。
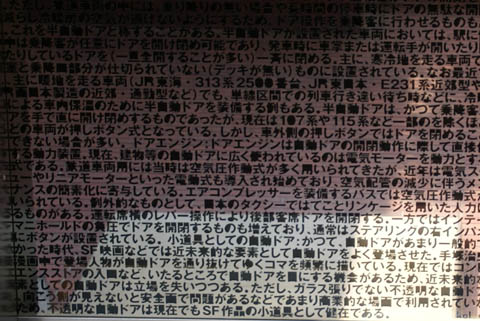
どうやら自動ドアに関する説明が書かれているので、
自動ドアかな、とドアの前に立つとやっぱり自動ドアでドアが開いて、
中は普通にかわいらしい服屋さんで思いっきり恥ずかしくて、そそくさと退散。

午後3時頃にギャラリーへ訪れると、中ではちょうど、
主催研究所の教授らしき人によるトークセミナーが開催中でした。
途中からの聴講だったのですが、とても面白かった。
南極観測所の建物は木造だという話には驚いた。
極寒という厳しい条件下では木造が最適なのだとか。
会場に展示してある模型群も興味を惹くものだったのですが、
一番惹かれたのはスライド資料で紹介された東大弥生講堂アネックス。

[東京大学弥生講堂アネックス(この画像はネットで拾ってきました)]
キャンデラのHPシェルを木造でやったようなその造形はすごく有機的。
東大の講堂といえば安田講堂しか知らなかったのですが、
他にもこんな素敵な講堂があったんだな。
人を惹きつけるが故に自ら富を産み、その財で自らのメンテナンスを行える。
そして良いものは長く使われ続ける。
エコの観点からも人を惹きつけるものを創ることはとても有効なのだ。
会場入口にある実物大作品その1。




ギャラリーそばに展示してある実物大作品その2。



中庭の端に展示されていた実物大作品その3。


...レーモンドのクロス梁に似てなくもない。
ギャラリー内にはもっと複雑で面白い造形の模型が展示されていたのだけど、
実物大の作品に比べると、なんかおもちゃのように思えて存在感を薄く感じてしまう。
やはり構造の魅力を伝えるにはスケールという要素を無視することができない、
ということを再認識させられた。
やはりできるだけ大きなものを作らねば。
東大にこんな面白い研究所が、しかも社会人向けのコースがあったなんて。
すごく興味があるけど、資格として「定職にあり、関連分野業務に2年以上従事」だって。
...だめじゃん。
東大の建築学部って安藤忠雄氏や藤森照信氏らがいるところだよね。
彼らとのつながりはないのだろうか。
...その辺も含めて相談してみたかったけれど、
その後授業で時間がなかったためおとなしく退散。