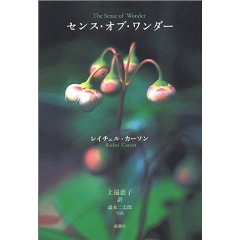けっこう前になにかの気まぐれで買ったのだけれど、
ろくに読まずに長い間本棚で眠っていた本。
『沈黙の春』を読んだのを機にようやく読みました。
海洋生物学者であったカーソンは、
ある1通の投書を機に環境問題の大著「沈黙の春」を執筆。
執筆中に癌が発症し、1962年の刊行からおよそ2年後に永眠。
本書は1956年にとある雑誌に掲載された原文を、
カーソンが最晩年に単行本として再編したもの。
実際は作業が完了する前にカーソンは倒れ、
友人たちの手により出版が実現したのだとか。
センス・オブ・ワンダー = 「神秘さや不思議さに目を見張る感性」
それは子供の頃には誰もが持っていた感性。
生物が真に幸せに生きていくために必要な感性。
...どうして大人になるとそんな大切な感性が失われていくのだろう。

300ページ以上にわたって辛辣な語り口で
自然の価値を忘れた人間の愚かさを批判する『沈黙の春』と比べて、
こちらは50ページ強と短く、あっという間に読み終える。
甥っ子のロジャーとの小さな冒険を通して「本質」を優しく説く。
やるべきことをやり尽くした後でのまさに締めくくり。
まさにこの本は『沈黙の春』のエピローグなのだろう。
もしもわたしが、すべての子どもの成長を見守る善良な妖精に話しかける力を持っているとしたら、世界中の子供に、生涯消えることのない「センス・オブ・ワンダー=神秘さや不思議さに目を見はる感性」を授けてほしいとたのむでしょう。この感性は大人になるとやってくる倦怠と幻滅、わたしたちが自然という源泉から遠ざかること、つまらない人工的なものに夢中になることなどに対する、かわらぬ解毒剤になるのです。~(中略)~わたしは、子どもにとっても、どのようにして子どもを教育すべきか頭をなやませている親にとっても、「知る」ことは「感じる」ことの半分も重要ではないと固く信じています。子どもたちがであう事実のひとつひとつが、やがて知識や知恵を生みだす種子だとしたら、さまざまな情緒やゆたかな感受性は、この種子をはぐくむ肥沃な土壌です。幼い子ども時代は、この土壌を耕すときです。美しいものを美しいと感じる感覚、新しいものや未知なものにふれたときの感覚、思いやり、憐れみ、賛嘆や愛情などのさまざまな形の感情がひとたびよびさまされると、次はその対象となるものについてもっとよく知りたいと思うようになります。そのようにして見つけだした知識は、しっかりと身につきます。消化する能力がまだそなわっていない子どもに、事実をうのみにさせるよりも、むしろ子どもが知りたがるような道を切りひらいてやることのほうがどんなに大切であるかわかりません...
一言でいうならば、ブルース・リーの「Don't think, feel.」ということでしょうか。
『沈黙の春』や『センス・オブ・ワンダー』が名著たるのは、
単なる自然愛好を説くのではなく、
人間が人間らしく生きるためのエッセンスが詰め込まれているから。
本質は変わらない。
だから時を越えて語り継がれる。
確かに科学技術は進んだ。
しかし人間は本当に昔に比べて賢くなったのだろうか。
相も変わらず人々の生活の中心はアスファルトに囲まれた都市の中にあり、
大切な自然環境をどんどん破壊していくばかりでなく、
すぐキレて、自分の親や子までも簡単に殺してしまうような殺伐とした社会で
人々は自らの社会を滅ぼそうとしている。
なんのために学んでいるのか分からず、
「みんながやるから」という他者依存では、
本当に自分がやるべきことなど見つかるはずもない。
この本を読んで、あらためて自分は今、知識を蓄えるのではなく、
失った(目覚めていない)感覚を呼び起こすために
大学に通っているのだということが分かった。
別に僕は自然主義を褒め讃えたいんじゃない。
自分がやるべきことを探求していきたいだけ。
しかし不思議なことにそんな風に探求していくと、
自然と「自然」に向かってゆく。
人間よ、自然に帰れ。
故郷の大地に帰れ。