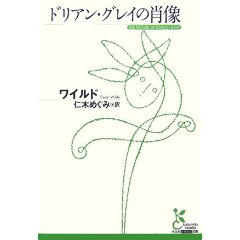特講Ⅰの授業でオスカー・ワイルドの「サロメ」を学んでいる、
ということもあって読みました。
オスカー・ワイルド唯一の長編小説。
...一冊で良かったのかもしれません。
全19章構成。
ドリアンの蒐集物を紹介する第11章の前半は要らない気がする。
彼の表現力は素晴らしいと思いますが、
そのすばらしさゆえに短い文章ですべてを表現できてしまう。
無駄に文章を長くしてしまうと今度は説教じみたものになってしまう。
ヘンリー卿の言葉を長く聞いていると、
親や先生に説教されてるような気になってしまうのは僕だけだろうか。
彼に唱えた芸術至上主義、快楽主義、個人主義、
そしてイギリスの「ダンディズム」をよく表している一冊だと思います。
人間は本能的に快楽を求める。
それは人生が辛く、はかないものだから。
しかし。
それでも人は快楽に身をまかせてはいけない。
自らを厳しい秩序で制限することで、人は幸せを感じることができるのだ。
人だけが感じることのできる快楽を享受できるのだ。

最初にスティーブン・フライ&ジュード・ロウによるワイルドの自伝映画を
見ていたこともあって、どうしてもヘンリー卿&ドリアンに彼らの姿を重ねてしまう。
それくらいこの小説はワイルド自身を投影しているように思えます。
もっともワイルドの最愛の恋人であるアルフレッド・ダグラス卿(愛称「ボジー」)とは
この小説がきっかけで出会うので、ドリアンのモデルは別にいたわけですが。
美青年ドリアン・グレイは画家バジル・ホールワードが描いた自身の肖像画を見て、
自身の美貌に気づくと同時に一時の若さの持つはかなさに絶望する。
そして思わず、肖像画の持つ永遠の若さと、自身が持つ「老い」とが
入れ替わればいいのに!と願う。
そしてバジルの友人の「ダンディー」ヘンリー・ウォットン卿の導きにより
ドリアンは快楽に耽り、堕落の道を突き進む。
ドリアンの願いを叶えたかのように、彼はいつまでも若く美しい一方で、
肖像画は日に日に老い、醜くなっていく...
そして彼が迎える結末とは...
この物語を彩るのはなんと言ってもヘンリー卿の言葉の数々でしょう。
快楽主義、芸術至上主義者であり、「ダンディー」でもあった彼は、
まさしくワイルド自身の言葉だった。
しかし快楽主義、芸術至上主義を説きながらも、
どこかでこれらの思想が理想であることを否定している節も見えなくもない。
その様子はドリアンが辿った結末からも伺えます。
「ダンディズム」というのは、表現される言葉そのものを
ただ単純に、正直に、そして真面目に受け止めるものではないらしい。
そのように受け止めることは本当にカッコ悪いし、
その表現に潜む本当の意味は見えてこない。
まずその表現が「美しい」が大前提で、内容が正しいか否かは二の次。
...というより正しいか否かは、表現を受け取るほうで考える。
どこまでもシニカルで、ニヒルで軽い。
しつこいと腹が立ってくるし、軽薄であるようにも見える。
しかしやっぱり本物の「ダンディ」は深い気がする。
本質が潜んでいると思う。
そんな「ダンディ」であるヘンリー卿の台詞を考察していきたいと思います。
「双方が偽りの生活を送ることが不可欠であるというのが、結婚の唯一の魅力だ。」
かつて「お互いの真実を共有すること」が結婚の唯一の魅力だと思っていた。
それで僕は失敗した。
人がエゴ、という厚い壁を持つ以上、どんなに愛していても、
すべての真実を共有することなど不可能だ。
そしてエゴの壁を乗り越えて愛を共有するためには、
真実だけではなく、偽りも共有しなければならない。
「いい影響などというものは存在しないんですよ、グレイさん。影響というのはつねに不道徳なものです。科学的見地から言って不道徳なんだ。」「どういうことです?」「人に影響を与えるというのは、その相手に自分の魂を与えることだからですよ。相手は自分本来の考えをなくし、本来の情熱で燃え上がらなくなる。その美徳さえ本来のものじゃなくなるんだ。その罪悪も、もし罪悪などというものがあるのならばだが、それさえも借り物になるのだ。彼は他人の音楽のこだまにすぎなくなり、自分のために書かれたのではない役を演じる俳優になる。人生の目的とは自己の開発にある。自分の本質を完全に理解する、そのために我々はここにいるのだ。最近では人々は自分をおそれている。あらゆる義務の中で、もっとも大切な義務を忘れている。自分自身に負っている義務だ。...」
エゴの外からの影響は自分自身を曇らせてしまう。
個人主義の究極的な性格。
もちろん極端であることは分かる。
しかし一方で真実も含んでいることは否めない。
社会が進歩すればするほど、人は他人に影響されるようになった。
それはそれで悪くないのだろうけど、
それで自分を見失う人も少なくない。
他人は自分を成長させてくれるけど、
自分をどのように成長させるかは、自分で自覚して決めなければならない。
「...ああ、ヘンリー卿!どうやったら若返れるのか、教えてくださらない?」ヘンリー卿は少し考えてから言った。「お若い頃にした大失敗を何か思い出せますか?公爵夫人?」彼はテーブル越しに彼女を見た。「おそろしくたくさん思い出せるわ」と彼女は答えた。「若さを取り戻すには、愚かな過ちを繰り返すだけでいいのです」彼女は叫んだ。「素敵なお説ね!やってみなくちゃ」...(中略)...「これこそが人生の偉大なる秘密なのです。最近の人々はたいてい常識病のようなものにいつの間にかやられて死ぬ。そしてもう手遅れになってから、決して後悔しないものは、自分の過ちだけなのだと初めて気づくのです」
若いうちはよく失敗する。
しかし、そのおかげで若者は成長できる。
大人になってある程度成功してしまうと、今度は失敗することを恐れるようになる。
言い換えればいつまでも失敗できる、ということが若さの秘訣ということでしょうか。
「一生に一度しか恋をしない人間こそ浅薄なんだよ。彼らが忠実とか貞節とか呼んでいるものは、習慣による惰性か想像力の欠如だ。感情生活において忠実であるということは、知的生活において堅実であることと同じだ。-単なる失敗の告白だよ。忠実!いつかこれも分析してみなければ。この中には所有欲が隠れている。我々には他の者に取られるのをおそれる気持ちがなければ、捨ててしまいたいようなものがたくさんある。...」
本当に必要でないならば、捨ててしまえばいいじゃないか。
それを他人にとられるとしても、自分には必要ないのだから。
「それは名誉なことだよ、ドリアンーすばらしく名誉なことだ。たいていの人間は生活という散文に投資しすぎて破産する。詩のために身を滅ぼすなんて尊敬に値する。...」
生きていくには生活していかなければならない。
しかし生活していくだけでは人は幸せにはなれない。
「より良く生きたい」という気持ちがなければ。
詩人はそのために詩を詠む。
「...僕が今まで知り合った芸術家の中で、人間として面白い人物はみな芸術家としてはだめだった。すぐれた芸術家というのは自らの作品の中にしか存在していないから、実生活ではとてもつまらない人間になってしまう。偉大な詩人ほど、真に偉大なる詩人ほど詩的でない生き物もいない。しかし才能のない詩人はおそろしく魅力的だよ。その詩が下手であればあるほど、人間としては輝いてくる。二流の十四行詩集(ソネット)を一冊出したことがあるというだけで、その男はたまらなく魅力的になるんだ。その男は自分に書けはしない詩を生きている。もう一方の詩人達は、現実に実行する勇気のないことを詩にしているんだ」
自らの中に芸術を持つか。
あるいは絵や彫刻、本、といった自らの外にある「モノ」に芸術を吹き込むか。
俳優や音楽家は前者であり、画家や彫刻家、小説家、詩人は後者である。
どちらを選ぶは人それぞれなんだろうけど、
両方を選ぶことは至難の業である、ということなんだろうね。
「他人のことをよく思おうとするのは、自分のことが心配だからだ。楽観論(オプティミズム)の根本には完全なる恐怖がある。我々は自分に利益をもたらしてくれそうな美点を持った隣人をつかまえて賛め、自分は寛大だと思っている。自分が引き出し超過になるかもしれないから銀行家をほめるし、自分の懐は狙わないでほしいから追いはぎにいい面を見いだす。今言ったことは、すべて本気で思っている。僕は楽観論をもっともさげすんでいる。だめになった人生について言えば、その人物の成長が止まっている人生ほどだめになっているものはない。」
人生には快楽と絶望の両側面がある。
絶望の恐怖から逃れるために人は楽観的になろうとする。
「なんとかなるさ」..と。
それは一種の逃避であると同時に幸せに生きるための処世術でもある。
絶望を一時忘れることで人は幸せになれる。
「快楽こそ論理を持つべき唯一のものだ」ヘンリー卿はゆっくりと音楽的な声で答えた。「しかし残念ながら、僕はその論理を自分のものだと言うわけにはいかない。僕ではなく『自然』の論理だ。快楽は自然の試練であり、自然が出す承認のサインだ。楽しいと感じるとき、我々はいいことをしている。しかしいいことをしているときに、いつも楽しいとは限らない」...(中略)...「いいことをするというのは、自分自身と調和することだ」ヘンリー卿は白く長い指の先で、グラスのきゃしゃな脚に触れながら言った。「不調和でいることは他人との調和を強いられる。自分自身の人生-それが重要なんだ。堅物やピューリタンになりたいと思うなら、隣人たちの人生について道徳的な意見をひけらかすこともできるだろうが、それは僕の知ったことではない。それに個人主義者にはもっとも崇高な目標があるからね。現代の道徳はその時代の基準を受け入れることで成り立っている。文化的な人間にとって、その時代の基準を受け入れることは、はなはだしい不道徳の一手段だと思う」「しかし、もちろん、自分のためだけに生きたら、ハリー、その人はそれによって大きな代償を払わなければいけないんじゃないか?」画家がきいた。「ああ、最近はすべてを大げさに言いすぎる。僕は貧しい者の本当の悲劇は、自己否認しか得られないことにあると考えている。美しき罪は美しい品々と同じように、富める者の特権なのだよ」
道徳は大事だ。
人が社会で共存していくために。
他人同士が同じ社会で幸せに生きて生きていくために必要な規範である。
しかし、いつの世も社会も変動する。
それに応じて道徳も変動する。
変わらない道徳などない。
当然、自分の本質にそぐわない道徳も存在する。
それは「悪」なのだろうか?
自分自身を否定してまで、他人から非難されてまで
消してしまわねばならない「悪」なのだろうか?
「あなたは前によい決意には不幸な運命がつきものだと言っていたでしょう-決心したときには、必ずもう遅いものだと。まさにそうなんだ」「よい決心というのは科学の法則を打ち破ろうという無意味な企てなのだ。その動機は単なる虚栄心で、その結果は完全に無だ。よい決心という奴はときどき、弱い者にとってはある種の魅力を持つつまらない感情を豪華に味わわせてくれる。それ以外に言えることはない。あれは口座を持っていない銀行から引き出す小切手のようなものだ」
良い決断かどうかは決断した後でなければ分からない。
決断するまでにそれが良いことか悪いことかくよくよ考えても仕方がない。
自分自身による決断であるかどうか、が重要なのだ。
それが分かっていても、やはり良いか悪いか迷ってしまう。
それは「弱さ」ということなんだろうね。
「人生は君にすべてを用意しているよ、ドリアン。君のそのすばらしい美貌をもってすれば、できないことなどなにもない」「でも、想像してよ、ハリー、僕はやつれて、年老いて、しわだらけになるだろう?そうしたらどうなる?」「ああ、そうしたら」ヘンリー卿は席を立ちながら言った。「そうしたら君は勝利のために戦わねばなくなる。今は君の手に黙って運ばれてくるもののためにね。いや、君はその美貌を失ってはいけない。今の時代は賢くなるために本を読みすぎ、美しくなるために考えすぎている。...」
人は若いうちに戦うのではなく、年老いてから戦うのだ。
「やる気」という気持ちと。
若いうちは理由がなくても前進できるエネルギーがあるが、
年老いてくると「理由」がなければ動けなくなる。
だから大人は「理由」を探すのだ。
「...ロマンスは繰り返しによって生きているのだ。そして繰り返しは欲望を芸術に変える。それに何度人を愛しても、その一つ一つがはじめての愛なのだ。対象が違っても情熱の一途さは変わらない。さらに強くなるだけだ。我々は一生のうちでせいぜい一度しか偉大な経験をすることができない。そして人生の秘密はその経験をできるだけ多く繰り返すことにあるんだ」「その経験に傷ついたとしても?ハリー」しばらく間をおいて公爵夫人はきいた。「傷ついた場合は特にだよ」とヘンリー卿は答える。
繰り返しはえてして退屈なもの。
しかし「偉大な経験」は希少だから偉大なのだ。
その経験を逃さないために人は繰り返さなければならないのだ。
「つくづく、女というのは危険なことが好きなんだな!」ヘンリー卿は笑った。「女の中で僕が特に愛する性質の一つだよ。他人の目がある限り、女はこの世の誰とでも恋愛沙汰を起こす」「つくづくあなたは危険なことを言うのが好きなんだね、ハリー!今回はあなたはひどく間違っている。僕は公爵夫人がとても好きだが、愛してはいない」「そして公爵夫人は君を熱愛しているが、そんなに好きじゃない。君たちはお似合いのカップルだ」...(中略)...「愛することができたらと思うよ」ドリアンは深い哀しみをこめて言った。「けれど僕は情熱を失い、欲望を忘れてしまったようだ。自分のことばかり考えすぎていたのだ。僕自身の個性が自分で重荷になってきた。僕は逃げ出したい。...」
「好きになる」ということと、「愛する」ということは違うのか?
「好きになる」ということは利己的であり、
「愛する」ということは他人のために何かしたい、という気持ちである。
それは自己犠牲なのか?
人は自己を犠牲にしてまでなぜ「愛する」のか?
そうすることで幸せになれることを知っているからか?
「彼をとても愛しているのか?」そう彼はきいた。彼女はすぐに答えずに景色を眺めながら立っていたが、やがて言った。「それがわかっていればいいのに」ヘンリー卿は首を振った。「知ってしまったら終わりだ。確信のなさが人を魅了する。霧がものを美しく見せるように」「道に迷ってしまうかもしれないわ」「すべての道は同じところに通じているんだよ、グラディス」「それはどんなところ?」「幻滅だ」「それがわたくしの人生の出発点だったわ」
「愛している」という気持ちは自覚できないものなのだろうか?
愛とは未知に対する希望なのだろうか。
既知となった時点で結果がどうあれ終わるものなのか?
時間を経て、お互いを知れば知るほど、
恋人たちが、夫婦が倦怠していくのはそういうことなのか?
「ハリー、もし僕がバジルを殺したと言ったらどうする?」ドリアンはそういった後、相手をじっと見つめた。「そう言ったらね、ドリアン、君は自分に似合わない役を気取っているんだな言うよ。犯罪とはみな卑俗なものだ。ちょうど、すべての卑俗さが犯罪であるのと同じように。ドリアン、君には殺人を犯す素質はない。こんなことを言って、君の自尊心を傷つけてしまったらすまない。けれど間違いなくそれは本当だ。犯罪は下層階級だけのものだ。彼らを責めるつもりはこれっぽちもないが。彼らにとっての犯罪は、僕らにとっての芸術のようなものじゃないかと思う。普通でない感覚を得るための方法というだけさ」「感覚を得るための方法?じゃあ一度殺人を犯した者は、同じことを何度も繰り返せると思うのか?そんなことはないよ」「ああ!どんなことでも繰り返せば快感になってくるものだよ」ヘンリー卿は笑いながら叫んだ。「これこそ人生のもっとも大きな秘密だ。だが僕は殺人はいつも間違いだと思う。食後の話題にできないようなことはするべきではない。...
ヘンリー軽い。
しかし間違ったことは言ってない。殺人はやはり間違いなのだと。
しかし人を見る目はない。
ドリアンはバジルを殺してしまっているのだから。
外見の美貌は所詮表面の浅さでしかない。
「美」とは表面上だけではなく、もっと奥深くにもある。
そして奥深くに潜む美こそ、真に美しい。
「ところでドリアン。『人が世界を手に入れても』、えーと、後は何だっけな?『魂を失ったら何の益がある?』」音が乱れ、ドリアンは驚いて友人を見つめた。「どうしてそんなことをきくんだ、ハリー?」ヘンリー卿は驚きに眉を上げて答えた。「ドリアン、君なら答えを教えてくれるかもしれないと思ったからきいたんだ。...(中略)...僕はその予言者に芸術には魂があるが、人間にはないと言ってやろうかと思った。だが、もし言っても、彼には理解できなかっただろう」「やめて、ハリー。魂はおそろしいほど現実的なものだよ。売ることも買うこともできる。それに何かと交換することも。毒すること多完璧にすることもできる。我々はそれぞれの魂を持っている。僕は知っている」「たしかにそう思うのか、ドリアン?」「たしかにそう思うよ」「ああ!じゃあそれはきっと幻想だ。人が完全に確信していることというのは決して真実ではない。これが『信仰』の致命的な欠陥であり、『ロマンス』の教訓なのだ。...」
魂を売り買いした結果に訪れるものは悲劇でしかない。
ドリアンが辿った結末のように。
あれだけ個人主義に傾倒しながら、都合のいいときだけ自己を放棄する。
そんなに世の中甘くない、ってことか。
やはりワイルドは快楽主義を、個人主義を疑問視している部分もあると思う。
「でもあなたは前に僕をある本で毒したでしょう。あれは許さない。ハリー、あの本はもう誰にも貸さないと約束して。あれは有害だ」「ドリアン、君は本当に説教を始めたね。君はそのうち改宗者や信仰復興論者みたいに歩きまわって、自分が飽きてしまった罪について人々に警告するのだろう。そんなことをするには、君には魅力がありすぎる。それに、そんなことをしても無駄だ。君と僕は今のままだし、これからも変わらない。本に毒されたと言ったが、そんなことはありえない。芸術には行動に影響を及ぼす力などない。行動への意欲を消してしまうんだ。すばらしく何も生み出さないんだ。世間の人が不道徳だと言う本は、世間の恥辱を示している本だ。それだけのことだ。...
このドリアンに悪影響を及ぼした本はユイスマンの「さかしま」なのだとか。
芸術が人に影響を及ぼすのはその「精神」だけなのだろうか。
人の行動に影響を及ぼすべく進化したものが「デザイン」なのだろうか。
ヘンリー卿と彼が送った本により、彼は自我に目覚めた。
しかし、彼はその自我の活かし方を誤った。
人は変わることができないというのは本当だろうか?彼はかつてヘンリー卿が白薔薇のような少年らしさと呼んだ、少年時代の汚れのない純粋さを激しく求めていた。自らを汚し、自らの心を堕落でいっぱいにし、自らの幻想に恐怖の翼を与えたことはわかっている。そして彼は他人に悪い影響を与えた。そうすることに激しい喜びを感じたのだ。さらに、彼の人生を横切った中で、もっとも公正で将来を嘱望されていた人々を恥辱にまみれさせたのだ。しかしそれはすべてもう取り返しがつかないのか?彼に希望はないのだろうか?ああ!高慢と劇場の瞬間に、肖像画が彼の日々の重荷を負い、自分は汚れを知らぬ輝かしい永遠の若さを失わないようにと祈ってしまった!彼の過ちのすべてはそこから始まっている。日々の中で罪を犯すたびに、すばやく確実に罰を受けていたほうがよかったのだ。罰には浄化の働きもある。「我らの罪を赦したまえ」ではなく「邪悪さゆえにわれらを打ちたまえ」のほうを公正なる神への祈りの言葉にするべきだ。
ヘンリー卿ははたして悪人だったのだろうか。
僕にはどうしても彼が悪人だったとは思えない。
ただ、ドリアンが弱かったのだと。
その弱さゆえに人の宿命を受けれず、悪魔に魂を売ってしまった。
彼が自分の過ちに気づき、改心しようとしたときは遅かった。
まさにヘンリー卿のいう、
「よい決心というのは科学の法則を打ち破ろうという無意味な企て」
に終わってしまった。
それでも人はやり直すことができる。
結果的には非業の死に終わってしまったけれど、
ドリアンは死の直前で救われたのだと思う。
彼は死の直前にして、幸せになることができたのだ。
...そう思おう。
ヘンリー卿のダンディズムはもちろん、
そのストーリーもやはり魅力的。
...ということでやはり映画化されているようです。
なんと本国イギリスで今年の9月に公開されたばかり。
ドリアンにはナルニア物語のカスピアン王子、ベン・バーンズ。
うーん、自分のイメージとしては金髪の美男子、
ジュード・ロウにやってほしかったなあ...
日本での公開はまだ未定とか。
見てみたい気はするけれど。
うーん、それにしてもこの本はやはり人を堕落させる。
課題そっちのけで一気に読んでしまった。
これもデカダンスの魔力なのだろうか...
追い込みをかけねば。